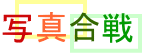
<三日目:昼休み>
「幸村!そっち行ったぜ!」
「来い佐助ェェェェ!!」
「嫌なこったー」
政宗の声を受けて佐助を待ち受ければ、いっそ誇らしく思えてしまうほど見事な身のこなしで佐助はひらりひらりと幸村の追跡をかわしてゆく。
やっと追い詰めたかと思えばとんでもない方へと身を躍らせ、思わずひきとめようとした幸村の手は虚しく空を切った。
「のわぁっ待て待て待て!!そっちは窓!!」
ここは四階だ。そして窓の外は職員駐車場だ。つまり、地面はコンクリート。
いくらなんでもこの高さから飛び降りれば佐助だってただでは済まないはずだ。
「佐助っ?!」
獲物として狙っているとしてもやはり佐助は大事な存在だ。コンクリートの地面へ真っ逆さまなんて事態となっては心配するに決まっている。
佐助が身を躍らせた窓へと慌てて駆け寄れば、一瞬ぶわりと風が舞いあがった。
「…っ!」
強すぎるその風に一瞬目を細めれば、幸村の後ろから追いついてきた政宗の声が響いた。
「上だ!」
「っ?!」
その声に反射で上を見上げれば、青空に浮き上がるように佐助のシルエットが屋根の上へと跳ね上がっていった。
どうやら飛び降りたと見せかけて屋上へ逃げたらしい。
「Shit!あいつは本物の猿か?!ちょろちょろ逃げ回りやがって…!」
「…くっ!追いかけまする!!」
なら己も、と窓枠に手をかけて身を乗り出せば、政宗があわてて幸村の襟首をつかんで引っ張り戻そうとしてくる。
「ちょっ?!お前も待て待て待て!!あの猿と自分を混同すんな!落ちるぞ!落ちても助けねぇぞ!!」
「これくらいの高さなど気合いで何とか!!」
「なるわけねぇだろ!!」
あわてて引き留めようと政宗がそう言ってくるが、すでに跳躍を始めていた体を腕一本で捕まえておけるはずがない。しかも政宗の手は幸村の襟首に引っ掛かっていただけである。
政宗だって軽く常識の枠内からはみ出ているほどの怪力だが、まずいことにそれは幸村にも言えることだった。
「Don't gimme shit!」
舌打ちした政宗の妙に発音の良い悪態を背に、幸村は窓の外へと飛び出した。
…と思ったが、外から飛び込んできた影にその体が押し戻される。
「…っ!!」
押し戻されるというより、足でふんずけられているといった表現のほうが近いか。
肩に感じる感触は確かに人の足で、痛くはないが何よりもまず腹が立つ。
「佐助ぇぇぇっ!!」
その足の持ち主など考えるまでもなく、己の腹からはドスの利いた声が飛び出した。
おまえよくも主を足蹴にしやがって。とりあえず一発殴らせろ。
そう思って拳を固めれば、佐助は飄々とした笑顔を浮かべて窓枠の部分に器用にしゃがみこんでいた。
「旦那ぁもうちょい考えて動きなって、危ないでしょーが…。俺様みたいな動きはちょっとコツがあるんだからさぁ」
「だからって足蹴にするか普通?!お前のほうが危ないわ!!」
「あんた口で言っても聞かないだろ?…ったく、あの体勢で飛び出したら真っ逆さまだっつの」
ぶつぶつと小声でつぶやく最後の言葉はうまく聞き取れなかったが、今はやっと巡ってきたシャッターチャンスだ。
カメラ。カメラを構えなければ。
そう幸村が思考したところで、背後から素早く誰かが飛び出すのを気配で感じた。床を蹴る見事な足捌きと空を切るような素早さ。
どれをどうとっても政宗以外あり得ない。
視界の端に移ったのは、この間のものよりずっとレトロなカメラを構えた政宗。
お互い精密機器とは相性が悪いということで、写真部から借りた丈夫さが取り柄のフィルムカメラだ。
「chekkmate!」
にやりと笑った政宗が、構えたカメラのシャッターを何度も切る。
佐助は目の前で相変わらず佇んだままだ。
やった、今度こそ写真が撮れた…!
三日目にしてやっと達成できたと幸村が思わず笑みを浮かべれば、佐助はやはり飄々とした笑顔で佇んでいて。
「……?」
常日頃から佐助は表情の読みにくい男であるが、付き合いの長い幸村にはこの手の笑顔があまり良い結果を招いたことがないことが分かった。
浮かべていた笑顔をわずかにひきつらせると、佐助がちょいちょいとどこかを指差した。
「What…?」
佐助の仕草に政宗も疑問をもったのか、幸村と同じように佐助が指を差したところへ視線を向ける。つまりカメラ付近にだ。
そして。
「「………っ?!」」
思わず二人同時に絶句すれば、佐助が音もなく横を歩き去っていった。
追いかけて捕まえたいが、捕まえてどうする。
目的の写真を撮るための道具は、使い物にならないのだから。
「く、そぉぉぉぉぉぉっ!!」
幸村は叫んだ。
レンズが真黒に塗りつぶされたカメラを睨みつけて。
<四日目:夜>
「よ、旦那」
一人ソファーに腰掛けるその背に向かって声をかければ、座っていた主、幸村がこちらへ顔を向けた。
「何だ佐助、敵情視察にでもきたのか」
不機嫌なのをまるで隠す気がないのか、幸村は座った目で佐助を睨みつけてくる。
言葉から何まで全部棘だらけだ。
「敵情視察ってあんたなぁ…、いつ俺様があんたに危害を加えましたか?むしろ俺様が獲物であんたが捕食者でしょーが」
「お前みたいな可愛くない獲物などいてたまるか。…捕食者側がおちょくられて終わりだろう」
むすっとした表情でそう言い捨てて、幸村はふいっと佐助から視線をそらしてしまった。
「うわぁ…」
これは完全に拗ねてしまっている。
さすがに連日幸村から逃げ回り続けていては機嫌が悪くなるだろうと思い、説得も兼ねてこうやって顔を出したのだが、既に遅かったらしい。
「でも俺様言ったじゃないの。写真は嫌いだって」
「その割にはのこのこと俺の家までやってきたではないか」
どうせ撮れやしないと思っているんだろう、と言葉にしない部分まで不貞腐れた雰囲気のオンパレードだ。
「俺様がここに来たのはカメラが無いって知ってるからだってば!部員でもないあんたらに部の備品を校外に持ち出す許可なんて下りないだろ!あのカメラ写真部のなんだからさっ」
「むぅ…」
馬鹿にしているわけではないと言い訳しても、やはり幸村の表情は晴れない。重苦しい声でひとつ唸っただけだった。
「だいたいなんで俺様の写真なんて欲しがるんだよ。別にそんなもの無くても問題ないだろ?」
「問題無くはない」
「……。」
きっぱりと返された答えに、流石に佐助も押し黙る。
「写真だけがすべてではないのは承知の上だが、もう少しお前だって何かを形に残したりするべきだ。中学の卒業の文集だってお前、何も書かなかっただろう」
「いやぁ、…まぁ」
それは『将来の夢』なんていう不透明なものについて書かされたからだ、と反論したいが、どうにも言葉が出てこない。
「お前がそういった個人の情報を残すことを嫌っているのは知っているがな、せめて少しくらいは妥協しろ」
でないと、本当は“お前はここにいなかったんじゃないだろうか”なんて馬鹿なことを考えてしまうだろう。
最後のほうは聞かせるつもりが無いような声量で呟かれたが、佐助の聴覚では簡単に拾えてしまう。
それを幸村は知っているだろうから、聞こえても聞こえなくてもいいと思っているのだろう。
「俺様はここにいるけど?」
「わかってる」
「顔だって毎日見飽きるくらい見てるでしょ」
「そうだな」
じゃあなんでそれで納得できないの?
佐助がそう聞くのを予想していたのか、ちゃんと言いきる前に幸村は声をかぶせてきた。
「でも、嫌なんだ。お前がいる証拠が欲しい。もっと痕跡も存在の証も己の姿も全部、消さずに残せ」
「………。」
話し方を変えればもっと茶化せるような話題ではあったが、こうも真剣に言い切られては流石に空気を変え切ることは難しい。
ここまで深く考えてもらうような内容ではないのだ。
ただ写真が嫌いなだけ。
人の記憶にではなく、形として己の姿が細部にわたるまで記録されてしまうのが、気持ち悪いだけなのだ。
薄れてぼやけてそのうち不鮮明になる人の記憶ならいざ知らず、形として姿がそっくりそのまま残ってしまえば忘れてもらうことすら難しい。だから写真が嫌い。
たったそれだけの、薄っぺらい内容なのだ。
「存在の証拠が欲しいなら髪でも切って渡そうか?」
「馬鹿者。遺髪みたいで縁起でもないだろうが」
「じゃあ爪とか?」
「お前な…俺がお前の爪なんぞを大事に保管しているところを想像してみろ、気持ち悪いだろうが」
「…確かに」
「ここは普通に思い出らしく写真だろう?そこまで俺は高望みしていないはずだぞ?なのに普通ならあるはずのものが無いからこんな強硬手段に出ておるのだろうが。お前が卒業アルバムにも集合写真にも個人写真にも全部載ってないから!」
「あー…だって写真嫌い」
「その問答は何度もした!」
いい加減腹が立ってきたのか、幸村が立ちあがって体ごとこちらへ向き直ってきた。
ソファを挟んで対面すると、相変わらずの幸村の表情がよく見える。やや血管の浮き出たこめかみと言い、あと少しで怒りが爆発しそうな予感満載だ。
「よく考えろ!今ここでこうやって喋っているお前と、十年後のお前の顔は全然違うのだぞ!後から見て懐かしむくらいの楽しみはあっていいはずだ!それに自分の顔を自分で見ることなど叶わぬのだぞ?!その時その時の表情を形に残すのは悪いことではないはずだ!」
「いやぁ…」
確かに幸村の言うことも間違いではないが、佐助にとってはできる限り回避したい事柄ばかりだ。
昔の自分の顔など適度に忘れてほしいものだし、普段己がどんな表情をしているかなど、感情の制御さえ忘れなければある程度把握はできるものだ。わざわざ形に残してまで確認するようなことではない。
それを幸村に理解してほしいとも思わないが、この場はどうにかして有耶無耶にしてしまいたい。でないと頑固な幸村は思いもよらない方法で佐助を納得させてしまいそうなのだ。
「佐助」
「はい?」
適当に誤魔化そうとしていることが読まれたのかと思い、内心ひやりとするが答えた声は変わらず平坦だ。
表情もいつもと変わらぬ飄々とした笑みを浮かべているはずで。
けれど幸村は、佐助のその飄々とした笑みへと手を伸ばしてきた。
避けるべきかと迷う隙に、頬を抓まれ痛くはない強さで引っ張られる。
「…なんれふか」
抵抗はしない。少々情けない声になったままだが、とりあえず問いかける。
すると、幸村が苦笑しながら手を離した。
「お前は知らぬだろう。普段どんな顔でお前が笑うのか」
「あんた曰く、掴みどころのない笑みでしょ?」
知っている。
作り笑顔の浮かべ方など息をするかの如く、だ。
しかし幸村は首を横へ振った。ゆっくりと、言い聞かせるように。
「大抵の場合はそうだろうな。…だが、たまに恐ろしく素の顔で笑うぞ、お前は」
「素の顔って…、」
どんな顔だ。
自分でもよく分かっていないと気づき、まさかこれが幸村の策略かと疑った。
己を把握していないことは佐助にとって恥となる。
素の顔とは何だ。そんなもの知らない。知っておきたい。
まさかこれが狙いだというのだろうか。
知らないものを知りたいと思わされることが策略だとしたら。
「…どうだ?少しは写真に興味が持てるだろう?」
「………。」
やっぱりこれは幸村の策略かもしれない。今の念押しのような言葉で余計のその疑惑が深まった。
ならばそれに乗せられるのは癪だ。
「別に、気にはならないね」
内心気にはなるものの、それを声には表わさず答えを返す。
「どうせそれ、あんたの前でだけだろうし」
己が素の顔で笑うというなら、この人の前以外では想像がつかない。
幸村以外の誰かが傍にいる状態で、己が素を見せることなどあり得ないのだ。
「俺の前だから気にならないのか…?」
佐助の言った意味がよく分かっていないのか、幸村は首をかしげた。変なところで敏いくせに、こういったところで鈍いのは相変わらずだ。
だから佐助は噛み砕いて、それはもう分かりやす過ぎるくらいの直球の言葉で言ってやった。
「俺様の見れない顔だろうがなんだろうが、見るのはあんただけで良いでしょ」
自分で見れなくても良い。
素の顔だろうが己の知らない顔だろうが、見せるのは幸村にだけだ。
ここまで言ってやっと幸村には通じたようで、悔しそうなとも嬉しそうなともとれる、何とも微妙な顔で固まっていた。
そんな主をその場に残し、佐助はひらひらと手を振って背を向ける。
「じゃ、写真はそろそろ諦めてくんな」
一言そう言い残して玄関へと足を進めれば、後ろから「絶対撮ってやるからな」という何ともありがたくない声が追いかけてきた。
幸村が諦めてくれるまで、まだもう少しかかりそうである。
<四日目:帰路>
「それにしても、“敵情視察”ね…」
幸村の家を訪れた際、一番初めに言われた言葉。
その言葉を反芻して、夜の闇に音として溶け込ませる。
「敵情視察、敵情、敵対する者の状況。敵、…は、“俺”」
ぞくり。
そこまで低くないはずの気温が、一気に下がったような気がした。
幸村がその言葉を発したあの瞬間、自分でも驚くほど動揺したのがわかった。…というより、動揺したことに動揺した。
言葉の綾と言えど、まさか幸村から敵呼ばわりされるとは。
たったそれだけで、本当に情けないくらい揺れた。
「俺様が“敵”ねぇ…」
仮に天と地がひっくりかえるような事態が起きたとして、己と主の関係もめちゃくちゃになったとしたら。
「それでも俺が真田幸村の敵にまわることはあり得ない」
断言できる。
それは無い。あり得ない。
だから、敵じゃない。
敵じゃないのだ。
「あーあ、ちょっとだけ後悔しちまったかも」
己が写真を嫌だ嫌だと逃げ回るからあんな風に幸村が拗ねて、敵情視察なんていう言葉が出てきたのだ。
そんな些細な言葉に揺れる己を知るくらいなら、己の主義くらいひん曲げて写真の一枚や二枚撮らせてやればよかった。
…ほんのちょっと、本当に少しだけ佐助はそう思った。