清めの火が焚かれたこの場所で、じっと空を見上げた。
炎凰の生みの親である鍛冶師達が集ったここは、集落から外れた開けた場所にある。
遮るもののない空は、三日月がぼんやりと光り星も密やかに瞬いている。
美しい夜空だ。
しかし一点だけ、異様なものが混じっている。
西の空が赤い。
あの場所へはかなり距離があるというのにこれだけの色がここからでもこんなにはっきりと見える。
そしておおうおおうと聞こえてくるのは何の声か。
腹の底から、胸の内から、頭の中から響いてくるその声。
込められた感情が怒りか喜びか悲しみかも判別つかない、それはただの激情。
思わず握った拳に力が入る。
他の者はこの声が聞こえていないのだろうか。周囲を見回しても空へ目を向けるものはおろか、呑み込まれそうなこの声に反応すらしない。
聞こえているのは、己のみか。
ではやはり、この声は炎凰。
己の槍。
迎えを待つような慎ましい気性など持ち合わせては居ないのだから、自ら動けぬ身だというのに荒々しく行く当ても無く進もうとしているのだろう。
ただ前へ。
その歩みが止まるのはこの手へ戻った時か、存在ごとその身が消え去った時の二つのみ。
それまでは決して諦めようとしないに決まっている。
そんな猪突猛進しか頭に無いあの槍を、奪還しに行った者たちを思うと、いてもたっても居られなくなる。
大したことじゃないとでも言うように笑いながら、ひらひらと舞う衣を翻して去っていった部下たち。
「こんな格好は普段しないから楽しい」何てこちらの気持ちを軽くするためについた他愛の無い冗談だと分かっている。
今あれほどの炎が上がっているような場所へ向かおうとしていたのだから、危険が無いわけ無いだろうに。
それでも楽しげに笑って、目に確かな怒りを熱を宿して行ってしまった。
見送る側がこんなに辛いとは、確かに知っていたはずなのに今まで忘れていた。
絶対に忘れないだろうと思っていた感情のはずなのに。
そう、それは戦へも出れぬ、まだ幼かったあの頃。
戦装束を身に纏い、背を向けていってしまう父の姿を何度も見送った。
その背を見ながら、いつになれば見送らずに済むのだろう、傍で、この大切な人を傷つけようとする何かから守れたら良いのにと、あれだけ願っていたのに。
あんな思い、忘れられるはずが無いと思っていたのに。
それなのに、今こんなことが起こってしまうまで忘れていたのだ。
武器を手にした理由は何だったか。
強くなると誓った理由は。
幼い頃、確かな思いを抱かせたその存在。
大切で、大好きだったあの父は、今はもういない。
戦の最中、どれだけ手を伸ばしても届かないところへ逝ってしまった。
誰かを失うのは苦しい。
大切な人がいなくなってしまうのは特に悲しい。
危険なところへ近づかないで欲しい。
いなくならないで欲しい。
一番駆けを競って真っ先に斬り込んでいく中、この身を守る者達はこんな思いをいつもしていたのだろうか。
胸が張り裂けそうだ。
出来ることなら今からでも飛んで行きたい。
けれど、それをしてはならないと師は言った。
耐えることも大切だ、と。
師の言葉に間違いは無い。
行っても迷惑をかけるだけだと分かっている。
そして己が隠密に向いていないことも。
しかし、この苦しみは尋常ではないのだ。
苦しくて苦しくて、おかしくなってしまいそうだ。
いつも傍にいてくれるのに、どうして今は遠くにいるのだろう。
お前たちの、…お前の在るべき場所はここなのに。
鉢巻一つ、髪を少し、そして六文銭。
たったそれだけしか渡せなかったのに、あんなに大事そうに握り締めるな。
もっと何か、深く刻み込めるものを渡せればよかったのに。
もっと存在を深く感じられる何かを。
けれど、そんなものが無いことくらいわかってる。
一番の望みは一緒に行くことだったのだから。
ああ。
傍へ行くことが出来ないのなら、せめて。
逝くなという当たり前の願いすら遠慮する、あの優しい影達の無事を祈ることくらい許してはもらえないだろうか。
「…早く、帰ってこい」
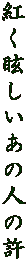
伸ばした指の先に触れる固い木の感触。
古い傷や、何度も触れたことによる削れなどがそこここに見当たる扉だが、丁寧に掃除をしているため何処か趣のある艶を纏っている。
その扉をゆっくりと開き、何処か埃っぽい、かび臭い室内へ足を踏み入れる。
ここも小まめに掃除しているのに、蔵という特性のためか、この臭いだけはどうにも落ちない。
入った瞬間のその臭いはあまり好きではないが、この空間はとても好きだった。
色んな物が押し込められたこの場所。
大切な物が保管されているから、小さい頃は絶対に入らせては貰えなかった。
大きくなった――と言っては初老を迎えたこの年では控えめ過ぎる表現だが――今ではもう誰にも咎められずに出入りできるが、今も昔も変わらぬ嬉しさを抱かせてくれる。
そんな子供めいた思いを抱きつつも、きしきしと音を立てて床を進み、奥に設えた棚の扉を開く。
きいと音を立てて開いたその中には、人の頭くらいの大きさの木箱が一つ。
そうっとそれを取り出して、ことんと軽い音を立てて床へと置いた。
表面が悲しげ曇るのを己で感じつつ、深くため息をつく。
そのまましばらく沈黙していたが、やがて意を決してその木の蓋を開いた。
ふわりと香る、虫除けの香。
露になったその中は、一応薄い布がくるりと収まっているものの、本来の中身は空。
木箱の主が不在のまま、それは丁寧に棚に仕舞ってあったのだ。
その様を見てまた一つ深いため息を吐きつつ、誰に話しかけるまでもなくゆったりと口を開いた。
「先祖より伝わるあの壷が消えてしまってからもうどれだけ経つだろうな…?お前も主不在のままでは寂しかろう」
どこか悲しげに木箱の縁をだどる仕草が、中身の大切さを物語っている。
本来この木箱の中には、壷が収まっていたのだ。
それも、とても大切な。
「賊か夜盗か、それとも壷が己から走って行ったのか…。そんなにこの家が嫌だったのだろうか?」
誰に知られることもなく姿を消した壷は、箱だけ残して今も戻らない。
折角銘の入った立派な箱だというのに、中身が空ではそんなもの何の価値も無い。
一体どこへいってしまったのか。
「せめて、倅に家を譲る前には戻ってきて欲しかったが…、それももう叶わぬか…」
健やかに育ってくれた上の息子は、もうこの家を任せても何も心配無いと言えるほどに成長した。
あの甲斐の国主から言葉が掛かれば直ぐ様馳せ参じる覚悟が消えることは無いが、体に無理が利かぬ年になってしまった。
それなら一線を退いて、妻と共に残りの余生を送っても良いだろう。
そう思って決めた当主拝命の日取りまであと僅か。
祈るように過ごす日々が、今日のように眠れない夜を齎している。
どうせ眠れぬ夜ならばと、一縷の望みに縋ってこんな意味のない確認作業を続けてしまっている。
早く区切りをつけなければ。
そのうち耄碌したとでも噂が立ってしまうかもしれない。
そう息をついて、何気なく明かり取りの窓へと目を遣った。
今日は何か祭りでもやっていたのだろうか、何故か空が赤い。
いやいやそんな話は聞いていない、それならもう夜が明けたのか。
いやしかし、それにしては月が高い。
「火事か?」
火消しの声が聞こえぬのだから、直ぐに皆を起こさなければ。
そう思って立ち上がった瞬間、その窓から何かが飛び込んできた。
「?!」
驚いて動けなくなった体を咄嗟に恥じたが、飛び込んできたそれはどうにも人の動きからは程遠い。
猿が寝ぼけたのだろうか?
念のため木箱を大事に抱えて後退さると、その猿…のような何かがむくりと立ち上がった。
何だか思ったより大きい。
「賊…か?」
これで「そうです」なんて答えられたらどうにも間抜けなやり取りになってしまうが、どうにも姿が派手すぎる。
神事で見かけるあの神に仕える者達の姿に似ている気がしたのだ。
袖がたっぷり採られた布地は神々しいまでの白。
それを彩る飾り紐は、どこか近しい武田の色。
髪は見事な銀色で、きらりと光ったその目は金か。
そしてどこかで見たことある仮面が顔半分を覆っている。
(…はて?)
こちらの疑問を余所に、そのどこか変わった侵入者は、衣擦れの音すらしない不思議な動きで床へ何かをことんと置いた。
「火薬か?」
戦場に慣れた己の思考回路のせいか、そんな不穏な言葉しか出てこない。
しかしそれを見た瞬間、体に震えが走った。
床に無造作に置かれたのは、凛と美しい輝きを放つ一つの壺。
「…それはっ、家宝の!!」
忘れもせぬその姿に思わず身を乗り出せば、謎の侵入者が一つ笑ってふわりと飛んだ。
「…っ貴殿!!待たれよ!!」
思わず呼びとめてしまったその声も虚しく、ひらりと軽やかに舞うその姿は動きを止めることはなかった。
来た時と同じく小さな明かりとりの窓からするりと抜けて、そのまま外へと消え去ってゆく。
せめて礼だけでも。
「どなたか知らぬが心から感謝致す!!」
叫べば空から…否、天井からぱらりと一枚の紙が落ちてきた。
どこにでもある様な和紙に、何かが朱墨で描かれている。
頼りない明かりの中それを確かめれば。
「……狐?」
そこには九つの尾を持つ不思議な狐が描かれていた。
それが舞い降りる様は、まるで天からの御遣いのようで。
口下手な己にはあるまじき言葉が脳裏に浮かび、思わず笑いそうになった。
背には三日月、両手に炎の翼を纏い、ゆっくりと降りてくる絢爛な姿。
常に付き纏うその身の闇は、夜のそれに溶け込んで酷く麗しい。
「…天へ還ってしまいそうだな」
己の感情のままにそう呟くと、受けとめるように両の手を伸ばした。
手のひら越しの姿が少しずつ大きくなってくる。
本来人が落下するであろう速度よりも明らかにゆっくり降りてくるのは何か術でも使っているのだろうか。
この手になかなか攫めないもどかしさがこの身を焦す。
たったこれだけの距離を埋める僅かな時間だというのに。
早く。
気が急いて仕方がない。
もっと早く降りて来い。
この手に。
「佐助!」
名前を呼んで、その身に手が届いた瞬間もう何も考えずにその身を抱きしめた。
「うえっ?!ちょっ苦し、ぐぇっ…掴む方間違えてません?!炎凰こっちだって!!!」
じたばたともがくのを気にせず腕にもう一度力を込めて、ずっと言いたかった言葉を放つ。
「良く戻った!!」
「うん分かったからその手を放そうね俺様帰ってきた瞬間にどこか遠くへ逝ってしまいそうだからっ」
「何?!」
さっきの懸念の通り、不穏な言葉を佐助の口から聞かされて、思わず腕に力が入る。
どこかへ行ってしまわないように。
「ちょっ苦しいっ…!!この馬鹿力っ!!は…放して…!!死ぬっ!!死ぬ〜〜〜!!!」
「うおっ?!すまん!!」
慌てて手を放せば地面へ佐助が崩れ落ちた。
その上何度も咳き込んでいる。
「さっ佐助!すまん…っ力加減を間違えたか?!」
「俺様は繊細なイキモノなんでもうちょい大切に扱って下さい…」
屈みこんでその顔を覗き見るが、飾り房がいくつも結わえてあるその髪が顔にかかってこちからかは表情が良く見えない。
しかも返ってきた声はどこまでも弱々しいもので。
「すっすまん!!」
感動の再会なのに何でさっきからこんなにも己は謝っているのだろう、と幸村は思ったが、佐助があまりにも辛そうだから何も言えない。
「だ…大丈夫か?!」
「あーうん大丈夫?…うん多分大丈夫。色々走馬燈みたいのが見えたけど」
「それは大丈夫なのか?!」
「や、大丈夫。…大丈夫」
自分に言い聞かせているようなその口ぶりに、さらに不安が増した。
「ほ…本当に大丈夫なのか?」
「うん大丈夫…。それよかもっと格好良く帰還させて下さいよ…全く」
がっくりと項垂れている姿が、何だか不憫に思えた。
佐助はどうにももっと格好つけて帰ってきたかったらしい。
幸村からしてみれば、空から舞い降りてくるあの姿だけでも十分格好良かったと思うのだが。
どちらかと言えば、あんな風にいつもの佐助と違う姿を見せられるより、常と変らぬこの姿の方を確かめたい。
特に、無事な姿を。
「…怪我は無いか?」
「今まさにあんたに背骨へし折られそうになってましたけど」
「あ…いや、その」
思わず口ごもれば、呆れたような笑顔の佐助が「どっこいせ」何て年寄りみたいなことを言って立ち上がった。
その両手には槍。
遠くへ在った時はあれほどまでにうるさかったというのに、今はとても大人しくしている。
主人の邪魔をしないように気を使っているのだろうか。
だとしたらとても出来た槍だ。
心の中で槍を賞賛しつつ、この手に収まるべきその姿を見れば、美しく澄んだ刃が幸村の目を綺麗に映し返した。
良い槍だ。
こっちにもちゃんと「良く戻った」と言ってやらなければならない。
そう思って手を伸ばそうとした瞬間、その身がひょいと離れた。
目で追えば、佐助が姿勢を正して炎凰を揃え持っている。
「…?」
どうしたのだろうと首を傾げれば、苦笑した佐助の目とかち合った。
「とりあえず、これくらいは格好つけさせて」
そう言って炎凰をふわりと振って、両の手で捧げ持つように揃え合わせた。
槍などあまり使っている姿は目にしないが、ひと通り武器には精通していると聞いたことがある。
だからこんなにも流れるように槍を操れるのは、そのせいなんだろう。
華美な衣装も相まって、その姿はひときわ美しく映った。
やはり、天へ還ってしまいそうだ。
じわりと滲み出そうになった不安を何とか己の中へ押し込めて、心を落ち着ける。
今は、そう。
炎凰の帰還の儀式だ。
気高いその身を、ふさわしい態度で受け止めなければいけない。
そう気持ちを切り替えて、口を真一文字へ引き結んだ。
そして身を起し、まっすぐに立つ。
それを目にした佐助が嬉しげに笑った気がした。
その表情をしっかり確認できないまま顔が伏せられ、同時に片膝が付かれる。
両手は前へ突き出したまま、炎凰を捧げ持って。
「貴方様の御槍、御身に纏いし紅蓮の字『炎』と、絢爛たる空の主、左右一対の翼の字『凰』を戴きし“炎凰”。この通り確かに帰還致しました。…どうかその御手に」
跪かれたまま静かに響く声と、刃に踊り始めた炎。
体全てでそれらを感じつつ、ゆっくりと手を伸ばした。
「いただこう」
己の声も、この者と同じように確かなものを宿して響いただろうか。
それを祈りながら、その槍を取った。
「炎凰、…良く戻った」
言った瞬間、炎が舞った。
この場所を照らしていた篝火の炎すら勢いを増して、天高く噴き上がる。
夜の闇が鮮やかな炎に照らされて、ここだけまるで夜が明けてしまったようだ。
きらりと光った両の刃が炎を噴き上げ、掴んだ柄からは紛れもない闘志が伝わってくる。
これから戦を共に闘う相棒だ。
これならば心強い。
「良い気性だ」
その勢いに満足して槍を一振りすると、さっきまでの炎が嘘のように掻き消える。
従順さも申し分ない。
「うむ。良い槍だ」
鍛冶師達にも聞こえる声でそう言えば、戻った事に涙していたその両目に、更に大量の涙が浮かぶ。
喜びで泣けるのなら、いくらでも流せばいい。
「これだけの者に想われていたのだから、次の戦で思う存分その力を揮ってもらうぞ?」
語り掛ければ確かな熱が柄から伝わってくる。
手に馴染む温かな意志だ。
それを手に受けたまま視線をずらして佐助のほうへと目をやると、その男は静かに佇んでいた。
改めて見ると、その姿はところどころ破れたり焦げたりしている。
片袖に至っては肩のあたりまで完全に燃え落ちてしまっている。…この槍の炎に焼かれたのだろうか。
知らず知らず柄を握る手にぎりりと力が入った。
「佐助…」
「あーそだ。六文銭返さなきゃね」
「いや…それは」
「これにはかなり助けられたよ…。ありがとね」
そう言って、そっけない仕草で幸村の首にちゃりんと音を立ててそれが掛けられた。
戦場では常に身に付けているこの印。
佐助の体温に温められていたそれは、違和感無く己の肌に馴染んだ。
「ちょーっと鉢巻に関しては使える状態じゃないんで…すんません、新しいの用意します」
そう言って振られた右手には、ところどころ血の滲んだ鉢巻が巻かれている。
少し破れたり焦げたりしているのは、それを身に付けていた部分が火に晒されたということで。
「佐助」
「あーあ、貸してもらうだけのはずだったのに悪いねぇ」
「佐助」
「って、俺がこんな風に使ったのをあんたに返せるわけ無いけど…」
「佐助っ!!」
思ったより声は大きく響いた。
自分でもびっくりしたほどだ。
けれど佐助は特に変わった様子もなく、いつものひょうひょうとした笑顔を浮かべている。
それでも、そのまま言葉を噤んでしまう訳にはいかなかった。
「笑ってごまかすな…。俺の炎がお前を焼いたか」
「掠り傷だけどね」
呆気なく肯定された言葉に、じくりと胸の奥が痛む。
「掠り傷、か…。浅くとも、多いな…?」
「どうだろ?」
肩をすくめて笑うその姿に、泣きそうになる。
せめて、一言詫びを。
「…す、」
駄目だ。
出かかった「すまなかった」という謝罪の言葉は、不意に胸の内に響いた制止の声に阻まれた。
言ってはいけない。
佐助は幸村に頭を下げられるのを、殊更嫌うのだ。
今こんな風に謝っても、佐助が胸を痛めるだけ。
主と忍の、越えられない壁はこんな時でもその存在を主張する。
そんなもの砕いて燃やしてやろうかとも思うけれど、それが出来ればこんな思いはしていない。
それならせめて。
「違う、言いたいのは。礼を、…礼の言葉を」
「…ん?」
「お前は俺が頭を下げるのは嫌いだろう」
「主人に頭下げられて喜ぶ忍っているの…?」
「国中探せばいるかもな」
そんな軽口を叩きつつ、炎凰を片手で抱えると空いた方の手で佐助の手を取った。
その手をゆっくり引きよせて、頬を寄せる。
「謝罪では無く感謝を。…良くやってくれた。お前がいてくれるから俺は戦える」
体温ごと伝われと祈りを込めて、出来うる限り真摯に紡いだ言葉は佐助へちゃんと届いたか。
視線の先の軽薄な笑顔は、不意に崩れて眉根が寄った。
「謝罪よか、…確かにそれのが嬉しいね」
それのどこが嬉しそうな表情なのか、はっきり言って理解できないが、佐助が嬉しいというのならそれでいいのだろう。
そう思って心のままに微笑んだ。
嬉しい時は、こうやって笑うのだと手本の意味を込めて。
「火傷に薬を塗らねばな。それくらいは俺にやらせろよ?」
「え…不器用なあんたに?」
「俺が薬を塗ると傷が早く治る気がしないか?」
「………する」
わりと本気でそう思ってそうな佐助を目に収めつつ、握ったままだった手を放して髪へ手をやった。
炎に焼かれて少し短くなったような気がする明るい色の髪は、やはり炎のせいで手触りが悪くなっている。
それを何となく勿体ないと思いつつ、褒めるように頭を撫でた。
「なんか俺様ガキんちょみてぇ。…頭撫でられるなんて」
「髪を触っているだけだ」
「…へいへい、でもまぁ、うちの連中が戻った時もその調子で褒めてやってよ」
「ああ…今は順調に怪盗中か?」
「怪盗じゃなくて義賊。石川五右衛門も真っ青じゃないのー」
「良いな。その名が霞むくらい派手にやってもらわねば」
「へへっ…夜が明けるのを楽しみにしときなよ」
そう言って笑った佐助の頭を相変わらず好き勝手撫でていると、不意に左手に抱えた炎凰から何かが聞こえた。
火の勢いそのままの熱を孕んだ声では無く、夜の闇のようなその声。
『会いたい』
確かに聞こえたその言葉は、なぜか佐助の声のように聞こえた。
望みを口にしない男が、ぽつりと漏らした奇跡のように。
「佐助」
「んー?」
「その、…よく帰って来た」
「それさっきも聞いたけど?」
平然と返された言葉に、負けじと言い返す。
「む…では、会いたかったぞ」
「って言っても、ほんの少ししか離れて無かったはずだけど?」
にやにやとどこか楽しげな様子がどうにも腹立たしい。
どうしてこんなに捻くれているのか。
そう思ってすうと息を吸い込むと、今度はもう一つ付け加えてこう言った。
「俺も、会いたかったぞ?」
「…え」
流石にこれには固まった佐助が、はっと炎凰を見た。
そして冷や汗を流しながら、幸村を見た。
「まさか…」
「良い槍だと思わぬか?」
にやりと笑って告げた言葉に、佐助の顔が引き攣った。
そして呻くように。
「伝言なんか頼んでねぇよこの馬鹿槍っ!!!」
大声で叫ばれたその罵声は、さっきの言葉を肯定するもので。
一つ笑って遠慮なく抱きつくと、また苦しいとか折れるとかいう軟弱な言葉が返ってきた。
そんなこと言っても、もう放してはやるまい。
希へ戻る ・ 終へ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
還る、はまんま帰還の話になりました。
ハロウィンの影響か知りませんが、何だか甘い…?気がします。
ですがこの二人、出来あがってません。
あと字=あざなと呼んでいただけるとありがたいです…。日本語って難しい。
仮面つけてお宅訪問してるのは才蔵です(ここに書かないと分からないという力不足…)
(08.11.3)