番いと引き裂かれるということは、己で言うところの片腕をもぎとられることに値するのだろうか。
あるべき場所からあるべきものが欠けた不自然な感覚。
確かに片腕を無くせば確かに動き辛いだろう。
けれど番うということは、二つで一つということ。
それなら、己は腕では無いのだから番いにはならないのだろう。
右腕には左腕、左腕には右腕。
それで一対なのだから。
それならば、あの手に馴染む得物の方が半身と言うには近いのかもしれない。
命を刈り取る業の刃。
それを操る己。
それを二つで一つと言い表すとは、なんとも自虐的で笑えてくる話だが片腕よりはまだ近いだろう。
けれど。
やはり、違和感は残る。
違うとどこかで思ってしまう。
こうして離れている今、あれの存在を感じることが出来なくても特に何も思わない。
使い慣れたあの武器の落ちない血の匂いなど、無くても既に己に染みついてしまっている。
斬る術ならこの腰に下げた飾り太刀でも十分なのだから。
ああ、それなら武器も半身では無いのだ。
じゃあ他は?
何があるのだろう。
思い浮かぶのは、常に付きまとう己の内側。
底の見えぬ闇。
やはり己の番いとは、この闇と言うことになるのだろうか。
切り離そうとしても切り離せない、この暗澹とした血泥の檻。
暗く深く絡みつき、己の魂すら染め上げたこの闇。
己の半分。
半身。
番い。
今引き裂かれている炎凰の片割れのように、片方が欠ければこのように怒り狂ったりするのだろうか。
『どこだ』と、声を荒げ探し求めるのだろうか。
行方を探して哭するのだろうか。
この闇を。
「境界すら曖昧なのに…?」
自嘲めいた笑みをのせてそう呟けば、答えは既に出ていたことに気がついた。
己と闇の境目には既にもう明確な線引きは存在しない。
つまり、二つで一つなんて言い表わす前に、もとから二つ存在していないのだ。
呼称が二つあるだけで、これはもう既に一つでしかない。
番う前に、最初から同じものだったのだ。
それなら、番いは。
「必要無い」
忍には必要無いものだ。
己を形作るものに番いなどあっては、欠けた時にどうする?
人としていつか失うかもしれないものを最初から捨てきって、そして出来たのか忍だ。
そんなもの、ある訳が無い。
なんて無意味な思考だったのだろうか。
ああ、けれど。
でも。
手に握る紅の柄から流れ込んでくる激情に、色々引き摺られそうになる。
片割れとか、番いとか。
今進む先にいるものが何かとか、そんなことよりも。
求めている、という行為に引き摺られる。
いつもはこんな風に思ったりしないのに、今は何だか少しおかしい。
脳裏に翻る赤が浮かぶ。
視界を埋める紅蓮に混じってあの姿が過る。
ここにはいないはずなのに。
何故映るのか。
これは炎凰の意思なのだろうか。
番いを呼ぶと共に、使い手のことも呼んでいるのだろうか。
だからこんなにも、感情が揺れるのだろうか。
呼吸すら乱れるほど、思ってしまうのだろうか。
こんなことを、考えてしまうのだろうか。
炎凰。
どうにも困ったことに、あの暑苦しい声が聞きたくて堪らない。
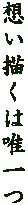
壁を越えようとする人間を引きずり落とし、にやりと笑んでそのまま意識を奪いとった瞬間、それは来た。
「………っぁ!」
ぞくりと背筋を這う悪寒。
気配と言うには鮮烈過ぎるその戦慄。
それは冷気だと思った。けれど、違った。
これは殺気だ。
炎を巻き込み、風が唸りを上げてぞわりと広がる。
まるで生き物のようだ。
木々を、壁を、人を巻き込み、なぎ倒し。
こちらへその手を伸ばしてくる。
「やばいっ…」
跳躍して避けても空は風の天下だ。逃げられるはずがない。
だから身を伏せた。
咄嗟に印を切り土を抉り、出来る限り身を低くしてやり過ごす。
この身が砕かれないことを祈りながら。
「………っ!!」
赤が風に煽られ色を変え、こちらへ牙をむいて迫ってくるのがよく見えた。
逃げるよりも止まることを選んだのは己、もうそれを見据えることしか道は無かった。
空気すら焼くつくすような炎が、すぐ目の前に。
呑ま、れ る。
「何やってんだこの阿呆っ!!!!!」
身へ刻んだ死への覚悟は、そんな罵声によって打ち砕かれた。
目の前に迫っていた火をかち割り、鮮やかな動きで爆風の発生源へと飛びかかるその姿。
幾つもの飾り房が軽やかに揺れて、翻ったのは少し焦げた片袖。
そして完全に露出した火傷交じりのもう片方の腕と、その手に握られたあのお方の槍。
「長…!!!」
呼べば頼もしい背がこの風の中でもはっきりと見えた。
そして遅れて音が届く。
金鎖よりも、深く重く温かく。
六文銭。
その音が向こう側にも届いたのだろうか。
唸りを上げていた炎が招くように道を開け、紅蓮の中にぽかりと空間が開く。
それによって見えた爆風の発生源。
そこへ目を凝らすと、ばさばさと衣をはためかせて佇む一人の男が見える。
いつもは鴉のように黒い髪は銀へ染め上げ、瞳は金に。
常から眉ひとつ碌に動かさぬその鉄面皮を憤怒に染め変えて佇むその姿。
その手には縋りつくように一本の槍が握られている。
ところどころ何かの紙が貼られた美しい輝きを放つその槍は、あの鍛冶師たちに見せられた炎凰の絵姿に似ている気がした。
炎を纏い、風を巻き込んで唸るそれは。
否、似ているのでは無い。
そのものだ。
「……っ!!」
何故その片割れが、ここに。
この爆風の理由を悟り、さあと血の気が引いた。
しかし長は容赦なく、佇む男の懐目掛けて鋭く飛び蹴りをかました。
あれは痛い。
「…っぐ、が」
呼吸が軋む不自然な呻き声共に、両の手からは彼の槍が離れ、ゆらりと宙を舞った。
その瞬間、柄をぱしりと掴む手が一つ。
その手には赤鉢巻が不恰好に巻かれている。
それを見届けて視線を下へ移すと、脇腹へ飛び蹴りを受けて吹っ飛んでいった男が見えた。
受身もまともに取れず、数度翻筋斗打ってやっと止まる。
死んだか。
思わずそう思って駆け寄ろうとした瞬間、すぐ傍で火柱が上がった。
焼けるような熱とともに視界を埋め尽くしたのは紅蓮。
それが上へと突き上げるように昇ってゆく。それはまるで飛翔のような。
空へ飛び去ってしまうかのようにも見えたその火柱は、彼の二槍へ宿ったあのお方の炎。
天高く翔け上がり、ここ一帯を焼き続けていた紅蓮すら巻き込んで高く空へ。
夜の帳が下りたはずの闇夜は、一気に紅蓮へと染め変えられてしまった。
昼間の様に照らされたその空は、炎の色。
これ程見事なものならば、今はここにいないあのお方の許へも届いただろうか。
「長」
二槍を手に真っ直ぐに立つその人を呼べば、仮面の内側に秘められた眼光がこちらを貫いた。
ゆるりと燻る怒りの熱が、闇を孕んで渦巻いている。
その迫力に一瞬びくりと身を震わせるも、その目はこちらからゆったりと逸らされ、地へ伏したまま咳き込んでいる男へ向けられた。
まともに話を出来るような状態にはとても見えないが、それでも長は容赦なく怒鳴りつけた。
「何やってやがるっ誰かれ構わず殺す気かっ?!」
「…っ!!」
地に伏した男…否、才蔵は起き上がって何か言い返そうとしたが、再度咳き込んで結局何も言えなかった。
それを無視して長はなおも続けた。
「とっとと正気に戻れこの阿呆っ!!自分の役目を忘れたか?!」
「奴らに…思い、知らせてやるっ…のだ」
「ちっ…この馬鹿がっ!」
舌打ちした長は才蔵へ近づいて行くと、やっと立ち上がりかけていた才蔵の体をもう一度蹴りつけた。
「いい加減にしやがれ!忍が感情に呑まれてどうする?!」
「…っ今日の俺たちは忍ではないと、そう言ったのはお前だっ!!」
今度は受身を取った才蔵はふらつきながらも怒鳴り返した。
ここまでこの男が怒りを露わにしたことなど過去一度もない。
ただの怒りならばこの男がこれほどまでに激することなどありえないはずなのに、今はまるで誰かが乗り移っているかの様に猛々しい。
言うなれば、炎のような気性の何かが。
(炎凰に、呑まれているのか…?)
不意に気付いたその可能性にぞっとした。
作戦立案の段階からずっと変わらなかった長の役目。
炎凰に直接触れる要の位置から動くことはなかった。
これがあるからなのだろうか。
怒り狂った炎凰は、人の感情すら呑みこんでしまうからなのだろうか。
だから。
長は。
叩きつけるような激情の嵐の中、その渦中から離れた位置でその様子を傍観していれば、長がひやりと冷徹な笑みを浮かべた。
「忍じゃない?はっ…そりゃ結構!俺は人でも無いとも言ったよな?だってのに実に人らしい感情に呑まれたもんだなぁ才蔵?これだけの炎が犇く中で良くもまぁ風なんて使えたもんだよ。“摩利支天”の名が泣くぜ?」
「主殿の御槍へのこんな仕打ちを目にして許せるものかっ!!」
「それが呑まれてるって言ってんだよ!碌な用意もせず軽々しくこの槍に触れんじゃねぇ!!死ぬ気か?!」
「俺ごときの命などっ!!」
そこで再度長の足が地を蹴った。
次いで鈍い音が響く。
「…っう」
横っ面を蹴り飛ばされた才蔵は、防御も間に合わず地面へ打ち付けられた。
下手すれば首ごとへし折れるような衝撃だっただろうに、それは何とか逃がしたらしい。
しかし流石にすぐには立ち直れず、伏したまま小刻みに震えている。
そこへ長が怒りを滲ませた声でこう告げた。
「その言葉、旦那の前で言ったらこれじゃ済ませねぇからな…」
「……。」
幸村様。
才蔵の口がそう動いた気がした。
途端、周囲の空気が凪いでゆく。
音にはされなかったその名は、我らが主の名前。
口に出せば無くしたと思っていた心に火が灯る。
泣きたくなるほど眩しいあのお方。
名前だけで、こんなにも心が熱くなる。
だから、それを才蔵が呟いたのも分かる。
この世のどんな言葉より、その身に深く響くのだから。
炎凰に引き摺られる形で怒りに呑まれていた才蔵は、感情の読みにくいいつもの表情へゆっくりと戻ってゆき、金に染め替えている目はいつもの光を湛え始めた。
何とか落ち着いたようだ。
「…ったく、俺ですら呑まれかけてんのに無茶すんじゃねえ。この槍の気性なんてお前も承知のはずだろうが」
「…ああ、もう、大丈夫だ」
答えた才蔵の声はところどころ掠れたものの、常とそう変わらぬものだった。
未だに揺れる頭を何とか正常に戻そうと、緩く頭を振ってふらつきながらも立ち上がろうとしている。
それに手を貸してやりながら長の方へ目を向ければ、未だに火を噴き上げ続けている炎凰をじっと支えて動かない姿が映った。
「長…?」
様子がどうにもおかしい。
柄を握り締める手は力を入れすぎて白くなっているし、仮面に覆われていない口元の部分は良く見れば固く引き結ばれている。
「長?」
再度呼ばわれば、苦しげな声で答えが返ってきた。
「…なんでもない。とっととここを片付けて帰るぞ」
なんでもないようには見えない。
そう言おうとしたけれど、喉まで出掛かったその言葉はぐしゃりと言う何かを握りつぶすような音に遮られた。
(…紙?)
空中で形を変えているそれは、文字の刻まれた不思議な紙切れだった。
炎凰に貼り付けられていたあれだ。
何故か宙に浮いたままの紙切れは、目に見えない力に押しつぶされているかのように、ぐしゃりぐしゃりと音を立てて小さくなってゆく。
それが豆粒ほどの大きさになった瞬間、ぼっといきなり火を灯した。
「火の玉…?」
宙に浮かんだまま燃えるそれは、墓場や戦場に偶に浮かんでいる火の玉に見えた。
灯った瞬間の赤は何故か暗く変じ、今は鉄錆色をしている。
これは一体何だ?
首を傾げたところでそれがいきなり爆ぜた。
「…っ!」
驚いて身構えるも、特に何も起こらない。
ただ鮮やかな火花を散らして、空気に溶けて霧散しただけだった。
一体なんだというのだろうか。
「才蔵」
こちらの疑問を余所に、長は淡々とその名を呼んだ。
「動けるか」
「無論」
問いかけに当然、と答えた才蔵はさっきまで立てなかったのが嘘のように軽やかに跳んで見せた。
「それじゃここは任せますかね」
笛を銜えた長がにやりと笑い、それと共に炎が唸った。
あんな笑い方をする時の長は、大抵怖いことを考えている。
これから向かう先に、何か恐怖を届けに行くらしい。
それだけ分かればもう十分だった。
己は尻尾。
この仮面の長の意思に従うまでだ。
両翼揃った炎凰の力は凄まじかった。
片翼でもあの強さだったのだ、それはもう本来の姿を取り戻したのであれば、その力は比では無い。
握りしめた柄の部分からあり得ない強さの激情が流れ込んでくる。
例えばそれは意思のようなものだろうか。
ぬらりと這った炎が探し求めているのは、あの三流術師。
愚かな呪法で炎を戒めた許しがたき人間。
そんなものを、炎凰が許すはず無かった。
出来ることならその怒りは幸村の手の中で揮って欲しかったけれど、今この手にその二槍を握りしめている佐助自身が一番良く分かっている。
それはもう叶わぬ事だと。
主の気質をそのまま表したかのようなこの二槍は、我慢なんて言う言葉を知らない。
己すら焼き殺してしまいそうなその熱を冷ますには、怒りを晴らすほか道は無かった。
両翼が揃ったあの瞬間、歓喜の声を上げ、そして直ぐ様その術師の姿を探し始めた炎凰の凄まじさと言ったらもうとんでもない。
頭の中をその思念が埋め尽くし、獅子の咆哮のように唸りを上げたのだから。
出来ることならその愚かな術師に聞かせてやりたい程の憤怒の大絶叫。
このさきしばらく夢に見そうなほどの迫力だった。
そして怒りまくった炎凰が取った行動は力技。
ごうごう炎を吹き上げ、ここら一帯をその術師ごと焼き尽くすことだった。
やっぱりとんでもない。
それを何とか宥めすかし、もともと切れかかっていた気力を総動員して別の道を見つけたのだ。
それがさっきの火の玉。
空中で霧散したのは術の残滓だった。
火伏せの呪を火で破られるとは何とも笑える話だが、散った火の粉はその憎き札を媒体としていたとしても十分働いてくれた。
術師のもとへ、還ってゆく力の流れが見える。
まるで獲物を捕える獣のように、炎はその通り道を邪魔することなく、泳がせて追いかけた。
頭の中に響きを持たない声が木霊する。
どこだどこだどこだどこだどこだ。
「…っは」
本来の使い手で無いこの身では、その声は重すぎる。
思考ごとそれ一色に塗りつぶされそうになって、それを抑え込もうとすれば呑みこまれ掛ける。
何とか逃れて、己の中の闇を意識して、そして首に掛ったこの印に縋って己を保った。
「必ず」
あの人がいない今、その影が代わりに役目を果たす。
行く先は既に定めてある。
地を蹴り風を切って進むこの先に、八つ裂きにしても足りないその術者がいるのだ。
怒りにただ炎をまき散らしていた炎がその矛先を定めた今、火消しに人員を割く必要がなくなった。
これでもう余計な心配する必要が無くなった。あの地は己の忠実な尻尾達が上手く片づけてくれる。
この身を引き止めるものは全て消え去った。
それならば思う存分この力を揮えばいいだけだ。
両の手に力を込めれば確かな感触が意思を伝えてくる。
それの赴くままに意識を研ぎ澄ませれば、目的の気配はもうすぐ傍だった。
屋敷から離れ、集落からも遠ざかったこの街道。
どこまでも愚かしいその術者は、炎が暴走を始めたと知った瞬間あの屋敷から逃げ出したらしい。
とんだ腰ぬけだ。
正面から相手をする度胸もないというのに、あのような忌まわしい呪でこの炎を縛るなど。
「愚か者が…」
声は己のものだった。
しかし込められた感情は多分この二槍のものだ。
空気を震わせたその音が通った場所から、紅蓮がちりりと走る。
そして仄かに咲いたその炎に向かって槍を振り、勢いを強くする。
目の前で踊っていた花弁ほどの大きさの炎が、一気に大きさを増して渦巻き始めた。
明かり一つ無かった常闇の中に、一気に浮かび上がった炎。
それを刃に乗せ、ずしりと重い二槍を握りしめ、そのまま思いっきり突き出した。
炎が唸りを上げて襲い掛かってゆく。
「思い知れ」
貴様らの封じ損なった炎の熱さを。
放った一波とともに己も飛び込み、記憶に残る主の姿を思い起こしながら槍を振りかぶった。
もう止まる気はない。
炎を纏いつつ空へ舞い上がり、槍の重みとともに地面へ落下する。
そのまま奴らの正面へ静かに着地すれば、悲鳴が上がった。
「ひっ…」
相手の術者は全部で七人。
術の系統から一人ではないことは分かっていた。
しかし負ける気はこれっぽっちもない。
一人残らず駆逐してやる。
「…天罰を、下しに来たよ」
炎に巻かれて騒然となっているその場でそう呟けば、声は驚くほどよく通った。
奴らにはこの身はどのように映っているのだろうか。
封じられたはずの炎凰を手に空から舞い降りて、炎を纏いながらそんな言葉を吐いて。
そしてこの派手な衣をはためかせて今佇んでいるのだ。
さぞ恐ろしいだろう。
恐怖に慄く術者たちの表情が酷く心地よい。
それを今から苦悶の表情へ塗り替えてやるのだ。炎凰の受けた屈辱以上の苦しみを奴らに。
口元をにやりと歪ませると、手に握った炎凰を記憶の通りに構えた。
目を閉じなくとも思い浮かぶあの苛烈な姿。
それを真似ればいい。
使い慣れたあの手裏剣の重みとはほど遠い重量感が腕を軋ませたが、この際それはもう無視だ。
笑みの形に歪めた口を、そのままぎりりと噛みしめて、一気に足に力を込めた。
耳元で風の流れる涼しげな音が鳴り、次いでがちんと金属が打ちあわされる音が響く。
生意気なことに相手は刃で受けとめたらしい。
しかしそれは意味をなさないことだった。
もともとこの大切な主の槍を傷つけるような真似をする気はない。
奴らを裁くのは、炎でだ。
受けとめられた刃の部分から、ごうと炎が噴き上がった。
それは一瞬で燃え広がり、敵の体を包み込む。
「ぎゃああああっ」
熱さにのた打ち回るその身を蹴り飛ばし、次の者へと目を向けた。
「次だ」
静かに呟けば、あの忌まわしい札がこちらへ放たれた。
避けようと思えば避けられた。
しかしそのままじっと動かずにいと笑う。
その札がこちらへ届く前に、それは空中でいきなり燃え落ちた。
格が違いすぎるのだ。
「無駄だよ」
死を宣告するように告げれば、それを肯定するかのように炎が更に勢いを増した。
その熱風に髪を煽られ、闇と炎が作った陰影の中でまた一つ笑んでやった。
さっきからずっと響き続けている一人目の悲鳴を背に、強く柄を握り締める。
「き…貴様っ」
「黙れ」
口を開いたその男に向かって槍を向ければ、炎凰が食らいつくように炎を翻した。
咄嗟に札を盾に防いだものの、あんな札では気休めにすらなりはしない。
あっというまに炎に包まれ、あたりに響く悲鳴が二つに増えた。
「次は誰?」
「…ひっ」
「お前かい?」
小さく悲鳴を上げた者のすぐ横に一呼吸で移動すると、びくりと引き攣ったその体を蹴り倒してまたも燃やした。
悲鳴が三つに増えるかと思えば、一人目の悲鳴が途切れてしまっている。
何気なくそちらを見やれば炭になっていた。
流石は炎凰の劫火。使い手以外が揮った力でさえ、これほどの火力を持つとは。
やはり、早くその身をあるべき場所へ返さなければいけない。
「それじゃ次」
そう言って槍を向ければ、全員がじりじりと後ずさりを始めた。
またも逃げる気なのだろうか。
「逃がさないよ」
宣言とともに身を低く構えれば、ごうと炎が唸った。
それは佐助の意思などお構いなしに、だんだん勢いを増してゆく。
「炎、凰っ?!」
あまりの強さに体が軋み、唸る激情が内側を支配する。
許さない。
唯一つ、どこまでも純粋な意志が咆哮を上げ、その瞬間佐助の体は自由を失った。
柄を握った手すら焼くほどの熱がごうと渦巻き、一人一人嬲るように揺らめいていた炎が桁違いに大きくなる。
それは地面の草木を巻き込み、暗闇を切り裂くように残りの術者達を一気に包み込んだ。
一斉に上がった断末魔の声。
熱風が吹き荒れ、纏った装束がちりりと音を立てて焦げる。
体も同じように焼けるような心地を覚えたが、痛みが麻痺していて何も感じない。
(……!!!)
声にならぬ叫び声をあげ、必死に体の自由を取り戻そうともがいた。
しかし腕に力を込めようにも何処へそれを向ければ良いか分からない。
このままではまずい。
今の状態すら上手く把握できていないというのに、ただまずいということだけが分かる。
長年培ってきた忍の勘だ。
それが逃げろ逃げろと警鐘を鳴らし、この状態を一刻も早く打破しろと囁き掛けてくる。
その声に抗うことなく、ただもがいて行方の分からぬ四肢へ向かってひたすら力を込め続けた。
その時、何かが切れる音を聴覚が捉えた。
この熱風が吹き荒れる中にぷちりと響いた小さなその音。
それが何かを理解する前に、胸元で確かに存在を主張していた重みが消えているのに気がついた。
「……ぁっ」
慌てて目で探せば、一つにまとめられていたその六文がばらばらに分かれて空へ跳んでゆくのが見えた。
頭の中が真っ白になる。
ただ我武者羅に、何も考えずに手を伸ばした。
そして指を広げ、それを掴む。
一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
あと一つは。
忍の卓越した視力が残り一つを見失うことはなく、くるくると跳んでゆくそれをじっと見据えたままこの足が地を蹴った。
円く軌跡を描いて落下してくるそれに向かって、限界まで腕を伸ばす。
落とさないように。
無くさないように。
指を広げ、掴み取る。
「……っう」
その感触を手に感じた瞬間、不意に己の体勢に気がついた。
六文銭に気を取られていたせいで、受身など取り様の無いほど傾いだこの体。
体勢を整えるにはもう手遅れで、危ないと思った瞬間にはもう派手な音を立てて地面を滑り転がっていた。
只でさえ火傷を負っている体を容赦なく砂利が引き裂いてゆく。
「……いっっっ!!」
筆舌尽くしがたい痛みが全身を襲い、思わず喉から悲鳴が漏れた。
起き上がろうにも起き上がれず、暫し体を丸めてその痛みに耐える。腕やら肩やら腰やらからずきんずきんと響いてくる痛みに泣きそうだ。
息を詰めてその痛みが引いてゆくのを待ち、動ける程度に回復したところでそっと手を開いた。
鈍く炎を照り返す輝きが六つ揃っている。
どれも無くさずに済んだらしい。
それを確かめて、ほうと安堵の息を吐いた。
そのままぐったりと寝てしまいたいほど疲れていたが、今これだけしんどい思いをしてこんな仮装をしているのは全て炎凰のためだ。
どんなに疲れていようと、無視して帰るわけにはいかない。
たとえさっき焼き殺されそうになったとしても。
嫌々ながら己をなだめ、炎凰が居るであろう位置へと目を向けた。
「うわぁ…」
佐助が絶句するほどの光景。
地へ突き立った炎凰を中心に、綺麗に円を描いて何もかも燃え尽くされている。
そこには草木の一本も残っておらず、燃え滓すら見当たらなかった。
何とか認識できるものといったら、この先しばらく植物が生きられないような色をした土のみ。
どこの破壊神の大暴れだ。
「ちょっと炎凰…」
げんなりと名前を呼べば、屈辱を晴らしたことで満足したのか、さっきよりずいぶん穏やかな炎が揺らめいた。
「いい加減にしてくれよ…。俺様は旦那じゃないんだからさぁ、あんなことされたら普通に死ぬっての!」
ぶちぶち文句を言いつつ起き上がれば、体中がびりっと痛んだ。
「う…っつう…」
痛みを堪えながらさくさく音を立てて死んだ土の上を近づけば、炎凰の下にひっそりと落ちる何かを見つけた。
「…?」
傍に屈んでそれを拾えば、それが何かすぐに分かった。
六文銭を繋いでいた紐だ。
「流石のお前もこれは燃やせねぇわな…」
苦笑しながらその紐に六文銭を通し首へかけると、器用に切れた部分を結び合わせた。
帰ったらこの紐は付け替えなくてはいけないだろう。
けれど今は、このまま下げさせてほしい。
この紐も含めて、あの人から借り受けたのだから。それを手放すことなんで出来るわけがない。
「さて、お前をあるべき場所へ返しにいかなきゃね」
そう言って炎凰の柄を掴み、焼け焦げた大地から刃を引き抜いた。
またも焼かれるか吹っ飛ばされるかするかとも思ったが、怒りを発散した炎凰はそこまで酷いことはせず、只真っ直ぐに使い手のもとへ行けることを喜んでいるようだった。
触れた部分から流れ込む思いが己と重なって、僅かに息が乱れる。
何故か胸の辺りが酷く苦しい。
このままじゃ会った瞬間に己が何を口走るか分かったものではない。
自制に関しては自信のある佐助だが、炎凰という感情の箍を破壊し尽くす存在がこの手にある以上楽観視は出来なかった。
だから、遠く離れたこの場所で、決して聞かれぬこの場所で、小さく一つ声に乗せた。
「会いたい」
憤へ戻る ・ 還へ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
希う、ということで強く願ってます。
周りから見たら無欲にも等しい望みでも、忍にとっては願うことすら躊躇うものだと良い。
…炎凰がますます捏造されているのには目をつぶって下さい。すみません。
(08.10.29)