熱い、熱い、熱い。
この心地は馴染み深い。
戦の中、あの人の傍で得物を振るう時と同じ感覚だ。
熱い、けれど嫌いじゃない。
これほど炎が近くにあるというのに、離れたくない。
火傷しそうだ。
この身が爛れそうだ。
けれど、傍に在りたい。
ああ、これはやはりあの人の炎だ。
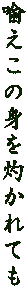
酷く愉快な気分だった。
いつもは暗く重たく感じる空気も、今は溶けるように軽い。
普段は晒さぬこの姿も、今は晒すためのものだ。
これだけ着飾ったのだから、見せなければいけない。
あの人も似合うと言っていた。
人の目に晒してもいい姿なのだろう。
それなら最上の方法で、恐怖を与えなければいけない。
人らしさを排除した動きで、力で、気配で。
やつらが仕出かしたことの重大さを思い知らせてやらなければいけない。
これは天罰だ。
今から己が下すのは裁きだ。
この姿を見て、慄けば良い。
悔やめばいい。
その罪深さを思い知れば良い。
許しを乞えばいい。
「許しはしないけれど」
そう唱えて、屋根の天辺へ躍り出た。
それと同時に、火薬を使って火の色を変える。
視線が集まる。
「上だ!」
踏みしめた屋根瓦の感触。
その足に感じる熱。
下から吹き上げる熱風。
それに翻ったこの装束。
ちゃりちゃりと鳴り続けるあの人の印。
辺りを彩る紅蓮の炎。
其の中に一点の白。
踊る金鎖。
しゃらりとなった軽やかなその音。
笑みを模る口元。
仮面に覆われた目元。
紅を巻いた片手を上げて、天を指す。
もう片方の手は己の真横へ伸ばす。
其の手の上に、狐火。
それがだんだん大きくなり、大屋根を焦がす炎に溶ける。
その瞬間、さあ、と音を立てて広がった紅炎。
下へ向かってぬらりと這い下り、総てを呑み込む。
下方で上がる悲鳴。
それを耳に受け、
「もっと泣き叫べ」
そう口にして前方へ体重をかけた。
体が前にゆっくりと傾ぐ。
そのまま倒れるようにゆらりと揺れて、瓦が顔の傍へくる頃合で地を蹴った。
滑るように屋根の傾斜にあわせて落ちる。
「妖狐だっ」
注意を促したつもりなのだろうか。
其の声が響いたときにはもうその声の主は意識を飛ばしていて。
わざと恐怖を煽るように、周囲の者へ向かってにやりと笑んでやった。
「もっ…物の怪っ!!」
上がったその言葉が気に入らないものだったため、空で印を切りその口を塞ぐ。
物の怪などと、見当違いも甚だしい。
「むぐっ…ぅ」
そのまま呼吸も止めてしまおうか?
そう耳元へ声だけ届けて、また嗤う。
「うっうう」
もがくその男をそのまま放置して、他のものへと目を向けた。
数人弓を構えている者がいる。
邪魔だ。
一つ袖を振ると、その動作一つで奴らは倒れた。
「ひぃっ」
怪しげな妖術とでも思ったのか、彼らは一目散に逃げていった。
実際は手練れである己の尻尾達へ合図を送っただけなのだが。
見た目の効果も相俟って、腕の振り一つでさえ何らかの術に見えるらしい。
大した事をしていないのに怯えられるのは面白くない。どうせならもっと凄いことをやって怯えて欲しい。
そう思ったが、逃げた彼らを追うのは己の仕事ではない。
やるべきことは唯一つ。
あの槍の奪還だ。
そう思って追いかけようとした体を踏みとどまらせ、手に灯したままだった狐火を腹いせとばかりに逃げるその背へぶん投げた。
「ぎゃあっ」
背を焼かれ、上がった悲鳴に少し機嫌を直し、次はこの場に残った者達へと目を向けた。
ひいふうみいよ、いつむうななや
人差し指を立てて、一人一人指を差して数え上げる。
そしてそのたびに「ぎゃっ」だとか「ひい」だとか、まるで死の宣告でも受けたかの様な悲鳴が上がった。
それが十回。
つまり全部で十人。
しかし数を把握したところで、辺りを見回すと、もう誰も残っていなかった。
全員地へ伏したまま動かなくなってしまっている。
「飛礫一発でこれかよ…」
天狐仮面はげんなりとぼやくと、手に残っていた飛礫をぱらぱらと地へ落とした。
指を差すついでにその眉間に向かって飛礫を飛ばしていたのだ。
あまり大きなものではない為、大した威力は持たないそれだが、まさか昏倒させるとは思っていなかった。
呆れるほどの打たれ弱さである。
しかし意識が残っている可能性も無いとは言えないので改めて踏みつけて確実に昏倒させておく。
「ぐえっ」
案の定呻き声が上がり、しっかり意識を飛ばしていなかったものも確実に落ちた。
これでもう、余計なことは考えなくても良いだろう。
「…本命はこっちだしね」
己の目的の場所へ体ごと向き直ると、ごうごうと火を噴く蔵が見えた。。
三つに絞った蔵のうちの一つ。
他の蔵と比べても大して炎の勢いは変わらないというのに、この蔵はどこか違う。
外見、造り、大きさ?
違う。
たぶん違うのは声だ。
中で何かを呼んでいる声がする。
助けて?
違う。
早く来て?
違う。
…もっと猛々しい何か。
何かを待ち受けるようなものではなく、自ら動けぬその身で、欠けた何かを探す声。
“どこだ”
それが近い。
足を斬られた武将が這ってでも進もうとするあの執念に似ている。
あの凄まじさ。
そんな声が、中から聞こえる。
絡め取られそうな思いと共に。
炎凰が求める狂おしいほどの何か。
それなら、それを叶える為にこの身が足になれば良い。
炎凰はこの先にいる。
「さて…」
入口を見遣れば火の勢いが凄い。
絶え間なく炎を吹き出し燃え盛るその蔵は、何故かこの身を誘うかのようにぽかりと口を開けている。
せっかく招いてくれているのだ、飛び込むならそこだろう。
しかしどう見ても中は灼熱だ。
このまま進めば炎凰のもとへ辿りつく前に焼き尽くされてしまうかもしれない。
だからと言って退くかと問われれば、それは否で。
既に心は決まってしまっているのだ。
「ま、死なない程度にね」
そう言って一つ笑うと、背後で働いている尻尾達へひらひら手を振った。
別れの挨拶でも何でもなく、ただの「行ってくる」の合図だった。
しかし答えが返ってきた。
その返答は多数の鈴の音。
しゃんしゃん響くその音は涼しげで綺麗だ。
少しはこの灼熱も冷めるだろうか。
そんな馬鹿なことを考えつつ、一言。
「それじゃ、いってきまーす」
やる気の感じられない声音でそう言い残し、そのまま蔵の中へと飛び込んだ。
今相手取っている敵は大した腕も持たぬただの破落戸だ。
しかし何故か項がちりちりする。
殺気とは違う嫌な何かだ。
これはおかしい。
ここまでの圧迫感を与えられるような相手はここにはいないはずなのに。
尻尾其の壱、もとい才蔵は目の前の破落戸を一撃で伸してぐるりと周囲を見渡した。
特に何も見当たらない。
けれどこの寒気にも似た感覚は無くならない。
何かがおかしい。
何か見過ごせないものが、確かにあるのだ。
きょろりきょろりと首をめぐらして辺りを窺っていると、その様子に気付いた他の面子が各々の相手を片付けて不思議そうに近寄ってきた。
「どうした?尻尾其の壱」
「何か感じないか?」
「…いや、特に」
「空気が張り詰めている。…何かある」
「長に何かあったかな」
「あいつは放っておけばいい」
『………。』
適当過ぎる返答に思わず絶句したほかの尻尾達だったが、辺りを見回す才蔵の様子は真剣だ。
笑い事では無いらしい。
「そういやちょっとぴりぴりするかもな」
「戦場の気配…と似た何かが」
「武器に手をやりたくなるね」
徐々に強くなる気配に、他の者も反応し始める。
けれど正体は未だに分からない。
「上から探そう」
そう言って跳躍した才蔵に続いて、他の尻尾達も一斉に屋根へと飛び乗った。
高い位置から見渡す景色は、何処もかしこも紅蓮が犇いている。
外へと消火に遣った尻尾達の尽力により、この敷地内から外へ燃え移ってはいないものの、このままではそれも時間の問題だ。
もうしばらくしたら、消火へ人員を増やさなければいけないかもしれない。
状況を冷静に整理しつつも、この謎の違和感を突き止めるために激しく燃える紅蓮の狭間に目を凝らした。
ここに来て昏倒させた者達が、端々にぶっ倒れている。
いい気味だと思うがそれらは今は関係ない。
ほかに何か、見当たらないだろうか。
「其の二、そっちはどうだ?」
「特になにも見当たらん」
「三は?」
「んー…分かんないね。ちょっとひとっ走り見てこようか?」
「それなら俺も回る。他は各自残存勢力の無力化、その合間に余力があれば鎮火に当たれ」
『御意』
揃ったその返答を聞いて、才蔵はその場から飛び去った。
其の三とは真逆のほうへと進み、この屋敷中を両端から探索する。そして半周すればかち合う。
言わなくても互いに心得ているやり方だ。
これだと効率が良い。
(それにしても、炎の勢いが強い)
違和感を感じた頃合から、炎の勢いが増しているような気がする。
まるで生きているかのようにうねる紅蓮は、瓦を這い回り、足場として着地した才蔵の足すら飲み込もうと手を伸ばしてくる。
ほんの少しその場に留まれば、一気に絡めとられてしまいそうだ。
屋根を移動するその一瞬でさえそうなのだから、中へ飛び込んだ佐助が今どんな状態にあるのか。
それを考えそうにもなるが、あの男のことだから、と思いなおして尚も進む。
無駄な思考よりも、この嫌な感覚だ。
こうして飛び回り目を凝らしても、特に引っ掛かるものは無い。
目に付くのは自ら拵えた意識のない人間だとか、燃え崩れた木片。
そして外へ逃れようとするこの屋敷の家人。
中には金目のものを持ってそのまま逃げようとする者までいて、ここの主の人望の無さが窺える。
風呂敷いっぱいに包んだのは壷か、箱型のものは茶器か。
懐に大事に仕舞いこんでいるのは燃え易いものだろう。
高価な織物か、絵師の名画か。
人の欲の浅ましさなど見慣れているため特に何も思うことは無いが、外へ逃すつもりは無い。
ここの家財は盗品も多いのだ。
後で盗賊団九尾が持ち主に返し、名を残す。
あの主が「それは良いことだな!」と快活に笑ったのだから、何としてもこれは譲れない。
だから今持ち逃げされては困る。
才蔵は懐から小さな笛を取り出し、鋭く息を吹き込んだ。
この笛は常人には聞き取れない音を出す。
忍寄せにはもってこいだった。これで今壁を越えようと走っている者達は、仲間の尻尾達によって道を阻まれるだろう。
そう思って別の場所へ目を遣った瞬間、大量の荷物を担いで走ってゆく家人たちの姿が目に映った。
手押し車を数人掛りで操りながら、大胆な火事場泥棒を行っている。
それに、何故か引き寄せられるように視線を持っていかれた。
逸らそうとしても逸らせない。
これは、何かある。
そう思って空中で印を切った。
この火の気の中、僅かに散った水の気を呼ぶ。
消火用に撒かれた水は方々に散っている。量は少ないながらもこれなら使える範囲内だ。
「冷気よ」
この熱さの中なら僅かな冷気でさえ酷く際立つ。
登場の演出としては申し分ない。
紅蓮が僅かに反発する心地を覚えたが、そこは無理やり押し切って冷気を奴らのもとへ注ぎ込んだ。
いきなり冷えた空気は、さぞ怖かろう。
才蔵は一つ大きく跳躍すると、突然の冷気に怯え足を止めた一団のもとへ真っ直ぐに落下した。
「ひっ…!」
四肢を地についてびたりと着地する。
もちろん音は立てない。
「もっ物の怪っ…!!」
さっきも佐助がこんなことを言われていたが、それは大きな間違いだ。
発光せんばかりの白を纏い、炎の担い手である彼の君の御槍を奪還する為に遣わされたこの身。
どうせなら御遣いと呼んで欲しい。
そんな思いを込めて顔を上げると、片手印を切って風を巻き起こした。
「ひぃぃぃっ」
情けなく悲鳴を上げて蹲ってしまったその一団を、ゆったりと見下ろし、次は何をしてやろうかと袖を振る。
そこで一人が念仏を唱え始めた。
失礼な奴だ、まずはこいつから黙らせよう。
そう決心したところで、その念仏を聞いた者達が泣き言のような懺悔を口にし始めた。
「おっお助けぇぇぇ!」
「やはり罰が当たったのだ…こんな、こんなっ」
「申し訳ありません神様仏様もうしませんんんっ!」
全力でそんな風に謝られても、才蔵には情けを掛ける気など一切起こらなかった。
むしろ煩くて敵わない。
そう思った才蔵は余計な演出を諦め、速さ優先でこいつらを黙らせることにした。
まずは念仏を唱えている奴を手刀で打ち据える。次は甲高い声が煩い初老の男を回し蹴りで。
そして残りは即効性の薬で黙らせた。
「……。」
静かになったところで一息吐くと、さっきから気になっていた積荷へ目を遣った。
どうにも妙な気配というのはこれのような気がするのだ。
こうも蔵だらけの屋敷なのだから、何かの呪いを受けた品があってもおかしくは無いだろうが、それにしてはやたらと引き寄せられる。これが悪いものならば、もっと本能的な危機感を覚えるはずだ。
それならば。
そう思って積荷の縄を切り、その中身を改めた。
「……?」
手押し車に積んであっただけあって、それは人が抱えるにはすこし大きめのものが乗せてある。
仏像や大柄の壷、そして一番目を引くのが布を何重にも巻きつけられた棒状の何か。
撒かれた布が多いのか、それとも中身が太いのか、人一人分ほどの大きさのものだ。
引き寄せられるまま手を伸ばすと、それは水でぐっしょり濡れていた。
「…?」
血かと思えば正真正銘の水である。
不思議に思いつつもその布を解くべく固く結ばれた結び目を切り払ってみると、さらに水が流れ出てくる。
包まれているのは植物かもしれない。
そう思いつつもぐいぐいと布を剥いでゆくと、やっと中の物の形が見え始めた。
やはり棒状の何かだ。片手で握れるほどの太さのように見える。
そろそろ巻かれている布も残すところ二枚か三枚か。
全部取っ払ってしまえば正体も分かるだろう。
そう思い布を剥ぐ作業を続けようと手を伸ばしたところで、全貌が見えないことに気づいた。
上の部分が他の荷物の下敷きになっているのだ。
引っ張り出そうとしても、何かがつっかえていて出てこない。
取り出すには上のものを退けなくてはいけないようだ。
そう思ってつっかえているその部分へ目を遣った。
そして見た。
見てしまった。
布の狭間から僅かに覗いた銀。
仄かな紅。
それを覆う紙切れ。
まず、体が震えた。
次いで呼吸が止まった。
噛みしめた奥歯がぎりりと鳴った。
目の前が霞んだ。
心が凍りついた。
ざわりと皮膚が粟立った。
怒りのあまりに。
蔵というものは、普通はもっと物が散乱していて、狭っ苦しい場所だと思っていた。
というより、真田の蔵はそんな感じだ。
良く分からないものが埃っぽく収められており、どこに何があるか何度見ても理解できない。
佐助もたまに入ったりするが、未だに蔵の中身を全て把握しきれていないほどの散らかり具合だ。
しかし今入り込んだこの蔵は全く違っていた。
まず広い。
そして物がない。
中を埋め尽くす炎が全て燃やしつくしたのかとも思ったが、それにしては燃え滓すら残っていないのだ。
ということは、わざわざ炎凰を収めるために、蔵一つ空けたのだろうか。
床はこの炎のせいでいまいち元の色が判別しにくいが、長い間同じ場所に物を置き続けて出来たであろう凹みが確認できる。
そして棚でも備え付けられていたような痕跡もある。
やはり、そうだ。
「で、どこよ?」
物がないのだから、見通しは良い。
しかし目的のものが見当たらない。
気配は嫌という程感じるのに、紅蓮一触に塗りつぶされたこの空間に、炎凰の姿は無かった。
そしておかしいのか、今のこの状態。
飛びこんですぐに炎凰を掴み捕り、そのまま飛び出す予定だったのだが、入ったところで何故かあまり熱さは感じなかった。
熱いことは熱いのだが、焼け死ぬほどではない。
それを不思議に思いつつも、捜索には都合がいいので理由を考えるのは止めた。
とりあえずは炎凰だ。
「こんな蔵に隠し部屋なんてあんのかねぇ…」
ぼやきつつも目算で間取りのおかしな部分を見極めてゆく。
隠し部屋は名の通り隠すための部屋だ。わざわざ分かりにくいように少しずつ寸法を狂わして出来た空間にひっそりと作る。
慣れない者には難しい作業だが、そう言ったものを見つけるのがこちらの本業だ。
出来ないなんてことはあり得ない。
「やっぱり外と少し寸法がおかしいや」
そう言ってどこか違和感のある壁付近へ歩を進めると、行く先の炎がふわりと道をあけた。
やはり何かが佐助を招いているらしい。
確信と言うより予感めいたものを感じて手を伸ばすと、そこには壁が一枚。
触れると音を立てて手を焼いた。
「…っ」
しかしそのまま手は離さずに、ゆったりと這わせて指で見つけたある一点で爪を立てる。
ぎしりと木が軋む音が聞こえて、そのまま壁が崩れた。
普通なら扉のように開くはずのその壁は、この炎に焼かれ続けた結果、形を留めておくことに限界が来ていたのだろう。
ばらばらと音を立てて残骸が落ちるその先には、思ったよりも広い空間が広がっていた。
と言うより、地下へと続く入口があった。
石段の組まれたその部分は、もともとは木で蓋がしてあったようだが、それも燃えて崩れている。
それを戒めていたであろう鎖ですら溶け落ちている。
赤く熱せられて散らばった破片が、目にも明らかなほど熱を伝えてくる。
地面であるこの石の階段も相当熱いのだろう。
「うへぇ…」
一瞬躊躇した佐助だが、先に進まねばここへ来た意味が無くなるのだ。そう言い聞かせてその地下へと足を踏み出した。
石段に足を吐いた瞬間、足を覆ったこの足袋が一瞬で燃え尽きることも覚悟していたが、幸運なことに高そうな白地の足袋は無事だった。
足下の焼け石も耐えられる範囲内の熱しか伝えてこない。
これなら進める。
いつまでこの効果が続くかは分からない今、ゆるりと進む気はない。
佐助は足に力を込めると、素早く駆けだした。
地下は狭いながらも紅蓮のお陰で視界は良い。
それに忍用の隠し通路でもないこの道は、常人用に作られているため立って駆けられるほどの広さだ。
忍の身では地を駆けるように容易い。
そのまま狭い階段を一気に駆けおり、平になったところですこし開けた場所に出た。
畳何畳分くらいの広さだろうか。
ざっと十六畳はありそうだ。
しかし上と違って見通しは良くはない。
天井からいくつもの鎖がぶら下がり、その先端には明かりをのせる為の燭台が括りつけられている。
その鎖というのが長く、視界を遮るように絡まり合っているのだ。
しかも何故かこの炎の中でも燃えていない不思議な紙が大量に貼られている。
それが余計に視界を阻んでいる。
「何この紙…」
邪魔でしかないその紙を手に取ってみると、あっという間に燃え尽きた。
他のも手に持てばその瞬間に一瞬で灰になる。
仕方なく手を触れずにそれへと目を凝らせば、表面にびっしりと文字が書いてあった。
佐助には読むことが出来ない言葉だが、見たところ梵字で書いてあるようだ。
しかし。
「これ…」
不意に気付いた。
どうも見たことがあるのだ。
たしかこれは。
「火伏せの呪っ?!」
理解した瞬間体が動いた。
腰から得物を抜き去ると、己に出来る最速の動きで札を斬り払う。
途中巻き込んだ鎖も一緒に切断し、がしゃりと音を立てて落ちた燭台を踏みつけ全て斬り刻んだ。
存在の一欠片まで消し去るつもりで。
がしゃんがしゃんと音を立てて燭台ごと破壊し、札を切り裂き、燃やし、そしてどんどん前へ進む。
視界を塞ぐ鎖も邪魔だ。
この札に関しては存在すらも煩わしい。
この世から消え去ればいいのだ。
そう思いを込めて、次々切り裂く。
派手な太刀が閃き、映る紅蓮が美しかった。
しかしそれを感じる暇もないくらい、目を汚すこの札が憎らしかった。
火伏せの呪。
それは火を抑え込む忌まわしい呪だった。
一般的には火の災厄除けとしての札が出回っているが、これはそんな優しいものではない。
三流術師が施した、愚かな力で火の気を無理やりねじ伏せる陰湿極まりない呪法だ。
力で叶わぬと知ってか、このような札を何枚も何枚も何枚も。
これを施した人間を、己は許しはまい。
紙の質は記憶した。
術の系統もある程度絞り込んだ。
あとはそう、見つけ出し、ありとあらゆる手段を持って、その所業を後悔させてやればいい。
そう仄暗く決意して、斬り払いつつも前へ進んだ。
そして一際強く燃え上がる炎の許へ一歩踏み出した瞬間、やっと辿り着いた。
あの声の主に。
「炎、凰…」
呼べば炎が鳴った。
鎖で雁字搦めに縛られて、その上からいくつも火伏せの札を貼り付けられ。
姿なんて見えやしない。
あの赤も、刃の銀も。
「炎凰っ」
この槍を前に武器を使うなんて無粋な真似は出来ない。
手にしていた太刀を腰へ戻し、手を使って札をはがし始めた。
いったいいくつ貼られているのだろうか。
こんなに沢山。
一枚一枚はがすなんてそんな面倒なことをやっていられる筈もなく、削ぎ落とすようにぐしゃぐしゃと剥ぎとった。手が熱で焼けるのなんて気にしていられない。
動きに合わせて胸のあたりで六文銭がちゃりちゃりと鳴ると、炎凰の生み出す炎が強まり、その身を戒める鎖を焼き切った。
ぶつりと切れた鎖は次々と地面へ落下し、さっき佐助が砕いた燭台とぶつかり合ってがしゃんと音をたてた。
その音すら耳に入らず、ぐしゃりぐしゃりと札を剥いでゆく。
こんなただの紙切れが、この気高い炎凰を戒め、力を抑え込み、苦しめていたのかと思うと怒りで我を忘れそうになる。
あの人の炎をこんなもので封じ込めるなど、許されることではない。
居に染まぬ相手の手に落ちただけでも許しがたいというのに、抵抗すら力ずくで封じられ、このように鎖でつながれ閉じ込められ。
どれほどの屈辱だっただろうか、炎凰。
「畜生っ」
一つ慟哭のような声を己に叩きつけ、最後の鎖ごと札を引き剥がせば、やっと戒め無しの炎凰の姿が目に入った。
すらりと伸びた朱色の柄と、地に突き立てられた銀の刃。
美しい輝きを放つ二槍。
…の筈が、一本。
たった一本しかない。
番いの槍なのに?
「おまえ…、」
声が震え、手も震え、伸ばした指先も震えていた。
身の内から湧きあがる激情が体の制御すら奪ってゆく。
「番いと、引き裂かれたのかっ…!」
喉が軋むような声で叫び、そのまま柄にそっと触れた。
その瞬間、焼けるような痛みとともに訪れた浮遊感。
「うぐっ」
どん、と鈍い音が体に直接響き、衝撃に頭が揺れた。受け身は一応取れたものの、石で組まれた壁に無理な体勢で叩きつけられれば流石にすぐには動けない。
そのまま地へ崩れ落ちると、あの人の印が高い音を立てた。
その音に、力が戻る。
ぐらりと揺れた頭を奮い立たせ、痛みに呻いた四肢を叱咤し、ふら付きながらも立ち上がる。
そしてもう一度炎凰の許へ。
「旦那の、槍…」
火が周りで踊っているのが見える。
そして地へ突き立った炎凰の片翼が見える。
今も絶えず、呼んでいる。
どこだ、どこだ、どこだ。
火を四肢の如く使い、番いの行方を捜し求め、哭するその姿。
相反するはずの言葉なのに、痛ましさと猛々しさというその二つがその身を彩るのに最も相応しい。
それに向かって、赤鉢巻が巻かれた右手を差し出した。
「その怒り、あの人の手の中で存分に揮いな」
相談でも持ち掛けるようにそう告げれば、ゆるりと渦巻いていた炎が佐助の右腕に巻き付いた。
赤鉢巻のあたりをぐるりと撫でて、肌を焼く。
右腕の袖の部分が、赤鉢巻を残して燃え落ちた。
ぱらりと音を立てて、行くあてを失った飾り紐が肩のあたりから垂れ下がる。
その先端すら、炎に翻り揺れて燃えた。
露になった腕を炎に焼かれながらもそのまま痛みごと熱を受け入れ、ゆっくりとその柄に触れてゆく。
指先からでなく、手のひらで、鉢巻の部分で。
「今は番いを迎えに行こう。…足は俺で我慢してくんな」
にやりと微笑んで柄を握り締めれば、答えるように炎がごうと鳴った。
そして触れた部分から炎凰の凄絶な怒りが流れ込んでくる。
常に冷たい闇の潜んだの己の奥底まで、すべて溶かされてしまいそうなその熱。
それに呑みこまれてしまわないように、胸に掛った六文銭へ左手を伸ばした。
触れればかちりと音を立てるあの人の印。
これだけは、この灼熱の中でさえ重く温かい。
それを一度だけ握りしめて、佐助はその場から立ち去った。
いつもの冷たい闇では無く、紅蓮の炎を纏って。
舞へ戻る ・ 希へ
---------------------------
憤る、なので皆さん怒ってます。
つがいを引き裂くのは罪。
炎凰は左翼と右翼が揃って一つの槍。
(08.10.21)