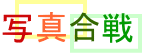
<五日目:夜>
「よ、旦那」
昨日の夜と同じく背後からかけれた声に振り向けば、やはり佐助の姿がそこにはあった。
しかし昨日の夜と明らかに違うところがある。
「おまっ…どうしたその傷は?!」
服からはみ出た素肌には包帯が見え隠れしており、顔にも傷を処置した跡がいくつもある。しかも血が滲んだ部分も多々あり、この傷を受けてそれほど時間が経っていないことが伺える。
「別に、ちょいとネガを処理してきただけだよ」
「ネ、ガ…?」
そう言われて、今しがたまで自分が眺めていた写真をさっと後ろに隠した。
「お前、政宗殿のところへ乗り込んだのか」
「まぁね。あと残ってるのはあんたが持ってるそれだけだよ」
に、と笑って指差された先には、この世で唯一と言っていい佐助の写真がある。
「それでその怪我か…」
「流石に竜の旦那は一筋縄ではいかないねぇ。最後は右目まで出てきたせいでこのざまだよ…ったく」
負傷は本意ではなかったようで、悔しげに佐助が笑う。
ここまで佐助が感情をあらわにするのは珍しいことだ。
「ま、目的はちゃーんと達成できたから良いんだけど」
明日学校行って独眼竜の顔見て笑ってやんな。
そう付け加えられた言葉に、この男が一方的にやられるような性格ではなかったと思いだした。
「喧嘩でも売ってきたのか…」
「そんなことしないよ。でもまぁ、今頃右目の旦那に説教くらってるんじゃない?」
「………。」
佐助が一体何を仕出かしたのか知らないが、政宗のもっとも苦手なものといったらあの世話役の小言だろう。
それを上手い具合に引き出したとなると、きっと碌でもない情報を流してきたのだろう。
「…性格の悪い」
「今さらでしょ」
開き直った笑みを浮かべながら、佐助はゆっくりと近づいてきた。いつもは匂いも足音も希薄な男だが、今は血と消毒液の匂いを漂わせている。
それが不快だとは思わないが、幸村は顔をしかめた。
「この写真も処分しにきたのか」
「…あんたが許可してくれるならね」
「するわけ無かろう」
そう言って背に庇った写真を守るように一歩下がれば、佐助は肩をすくめて見せた。
「そんな写真のどこが良いの」
そう言われて、隠していた写真を確認するように再度眺めた。
その中には、今にも相手を射殺しそうな目で見る者を睨む佐助が写っている。他のも数枚あるが、幸村が気に入っているのはこの一枚だ。
「俺様としてはそんな物騒な顔の写真は今すぐにでも処分してほしいんだけど…」
「断る」
「そんなあっさりと…」
「嫌だ」
「どうしても?」
「駄目だ」
「お願いします」
「却下」
「他の写真は残して良いから」
「全部残す」
「えー」
「“えー”じゃない!」
佐助の言葉をすべて却下すると、再度その写真へと目をやった。
やはり、殺気漂う表情で佐助がこちらを睨んでいる。
「うへぇ…やっぱり写真って嫌いだわ。何この顔。こんなの持ってても良いこと無いって」
いつの間にか背後から覗き込んでいた佐助に驚いたが、幸村の許可を貰えるなら処分する、といった佐助の言葉を信じ、隠すのはやめることにした。
今の体制では佐助も見づらいだろうと再度ソファへと腰を下ろしつつ、佐助の言葉へ答えを返す。
「確かに今にも殺されそうだな」
「そう思うなら処分してくれよ…」
げんなりと背後で吐きだされたため息に、幸村はそっと苦笑で返した。
「だがな、俺は気に入っている」
「趣味悪過ぎ」
「お前な…考えてもみろ、俺はこんなお前の表情なんて初めて見たぞ」
そうなのだ。
幸村は佐助のこんな顔は初めて見た。
何かの折に横顔くらいは見たことがあるかも知れないが、ここまで正面から射殺しそうな目で見られたことは一度だってない。
「当り前でしょ。あんたをこんな顔で見るようになったらそれは俺様じゃない」
「だからだ。見れぬものを見た。俺は嬉しい」
「…物好き」
「物好きで結構」
普通ならこんな怖い顔の写真など欲しくはないだろうが、幸村としては宝物同然だ。
怖い顔の佐助。
この表情の理由が幸村とあっては余計に大切に思えてくる。
佐助は怒りを覚えた時にこんな顔をするのだ。感情の起伏が極端に少ない佐助が、幸村が何者かに害された時だけ、こんなにも激しい気性を露わにして。
それのどこが嬉しいのかは分からないが、己が酷く満たされているような気がしたのでくすりと笑みをこぼす。
そうやって満足げに笑っていると、不服そうに佐助が背後で文句を口にした。
「せめて撮られるならもうちょいまともな顔のがよかったなぁ…」
「なら、今撮るか」
「はぁ?!」
条件反射なのか、佐助はしゅばっと幸村の背後から飛びのいた。
怪我をした状態でそこまで動けるという事実に関心しつつ、あと一台だけ残っていたデジタルカメラを懐から取り出す。
「あんた…まだそんなもの持ってたの…?」
「うむ。これが最後の一台だ」
「で、自分で使ったら壊すそれをどうする気?」
「お前が操作すれば問題無かろう」
「え、…撮るの?」
「何でもセルフタイマーというものがあるそうじゃないか。せっかくだし一緒に撮ろう」
初めの一日でデジカメの説明書は熟読してある。機能を試すところまでたどり着けてはいないが、必要事項はすべて頭に入っているのだ。この知識を生かせないのが残念極まりないが、それは己の力加減が下手なせいだと悔やむしかない。
「ほら、やってくれ。まだ充電は残ってるはずだぞ?」
「あのさぁ…俺様、写真が嫌いだから今日までずっと逃げ回ってたはずなんだけど」
「今さっき“撮られるならまともな顔が良い”と言ったではないか。普通の顔で写ればいい」
「いやいやいや…今の俺様ボロ雑巾みたいな有様だからね。怪我人怪我人」
「じゃあ記念に一枚」
「何の記念ですか」
「何でもいいさ。それより前言撤回などさせぬぞ?男に二言はないのだろう?」
にっこり笑って言ってやれば、佐助はしぶしぶながらもデジカメを操作し始めた。
幸村があれほど手こずった操作を軽々とやってしまうのは何やら悔しい気もするが、写真に写る気になったのならそれでいい。
「えーっととりあえず10秒で良いかな」
「それで良いぞ」
ちょうど良い位置にカメラをセットして、佐助が何やらボタンを押す。
「はい、あと10秒―」
「お前も写るんだぞ?こっちへ来い!」
「んー」
「佐助!」
「分かってますって…」
しぶしぶながらもやってきた佐助が、幸村の隣へ腰を下ろす。
「ほら、普通の顔をしろよ?」
「普通ってどんな…」
「とりあえず笑え!にぃって!」
「口の端切れてるから無理だって、痛いんだって」
「じゃあ切れてない方だけでも…」
「片方の口角上げた表情なんて完全に悪役の顔でしょうが」
佐助が困ったような声でそう言ったところで、ピピッと電信音が響き、その後にフラッシュが続いた。
「あ―――――ッ!お前がぶつくさ文句を言うから10秒経ってしまっただろうが!」
「今のはあんたも悪いって!」
あわててデジカメに駆け寄れば、既に写真は登録が終わっており撮影画面に切り替わっていた。
「佐助」
「あれ、そこは触って壊すかと思ったのに」
「…佐助」
「あーはいはいごめんなさい。やるやるやりますって。だから怒んないで」
幸村の手からデジカメを素早く受け取った佐助が、カチカチと画面を切り替える操作をしている。
意外とそれは簡単な手順のため、画面はすぐに切り替わった。
そして、映し出された写真に二人して口を噤む。
「「……。」」
きっと佐助も自分の表情を見ているはずだ。
そして言葉が出てこないらしい。
「なぁ佐助」
「なんですか」
「お前も良い顔で笑うようになっただろう?」
「うるさいですよ」
間髪いれずに返された声に、何とも言えない笑みがこぼれる。
その視線の先、佐助が手にしたデジカメには、いつも通り楽しげに笑う幸村と、伏し目がちに苦笑する佐助の姿が映っていた。
その佐助の表情は困ったような、呆れたような、それでもどこか楽しげな笑顔で。
「口の端が切れていて笑えないのだったか?」
「…あんたも性格悪くなったね」
「親しいものに似たのだろう」
にやりと笑って佐助の頭をくしゃりと撫でれば、佐助はそれはもう深いため息をついた。
早々に反論を諦めたらしい。
すっかり降参モードの佐助の手からデジカメを受け取ると、近々現像しなければと算段を付ける。
けれど、きっと現像してもアルバムには納めないのだろう。
人目に触れるのを佐助が嫌がるのだから、できる限り狭い範囲でとどめておきたい。
だから、箪笥の奥にでもしまっておいてやろうと思う。
そして本当にたまに、時折思い出す程度に取り出して眺めるのだ。
この貴重すぎる写真を。
<完>