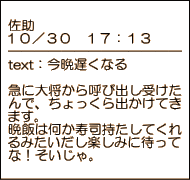ブラック・ブラック・ブラック
ブラック・ブラック・ブラック 
10月31日。
高校二年のこの秋を彩る大切な日。一年半以上もこの学校に在籍していれば、幸村の甘味好きなんて既に知れ渡っていて。
わざわざ「トリック・オア・トリート」なんて言わずとも目が合っただけで何かしら菓子を貰える幸せな日だ。
今日も剣道部の朝練を終えて教室へ戻る道すがら、何人かに菓子を貰った。
ハロウィンらしく黒とオレンジの小さな個袋に入れたものや、無造作にポケットに突っ込んであったもの。
食べようとしていたものを剥き身のまま口に放り込まれたものまである。
貰えるのはとても嬉しい。
嬉しいのだが。
「何故全員ブラックガムなのだ…」
口の中に広がる強烈なミントに耐えつつ呟けば、教室のドアが見えた。
HRが始まるまで少し時間がある。
クラスメイトに何か口直しになるようなものを強請れば良いだろう。そう思ってドアを開けた。
ガラリとやや耳障りな音を立てて開いたそれは、どうも掃除を怠っているようで砂を噛んだようにざりざりとした振動が手に伝わってくる。
教室掃除担当の班はどこだったか、と頭の隅で考えて、教室内へ目を向ければ既にほとんどの生徒が揃っている。
ぐるりと見渡せば、早速何人かと目が合った。
しかしそのうちの何名かに目を逸らされた。
手持ちの菓子が無いのだろうか。
そう思って視線を外さずにいてくれた者へ近づいていくと、こちらが何か言う前に「悪戯しないで下さい」と菓子を手渡された。
流石にブラックガムをずっと噛み続けているのは辛い、さっさと捨てて今貰ったものを食べよう。
そう思って手渡されたその菓子に目を遣ると、なんとそれもブラックガムだった。
「なっ…?!」
朝から連続でブラックガム。
目を覚ますにしても量が多すぎる。
そして己は今糖分を欲しているのだ。
具体的に言えばクッキーとかチョコとか団子とか!
救いを求めて他のものへと目を遣れば、無常にも全員からこれまたブラックガムを手渡された。
「……っ」
流石にこれを偶然と呼ぶには出来すぎている。
騙され易い己といえど、それくらいは分かる。
そして今の現状を引き起こした原因について、心当たりも無いとは言えなかった。
「佐助…」
「ん?おはよう旦那」
「佐助…、これは」
「お・は・よ・う・旦・那・?」
「お…おはよう」
やっぱり怒っている。
己の顔が引き攣るのを感じつつも、ここで諦めるわけにはいかない。
なんて言ったって掛かっているのは今日一日でもらえるはずのたくさんのお菓子。
たとえ佐助が怖くとも、ここは勇気を振り絞っていくべきところだ。
「佐助、こ…これはお前の仕業か」
聞くまでも無くそうに決まっているが、念のため聞いておく。
詰問の枕詞のようなものだ。
しかし詰問云々と言う前に、佐助の怒りが深過ぎた。
「これって何のこと?」
「いや…、その」
「俺の仕業って何?」
「そ、それはこのブラックガ…」
「旦那ぁ、まさか昨日あんたが仕出かした事忘れたわけじゃないよね?」
「そ、その…」
「それ踏まえた上で、今日皆からお菓子を貰うつもりしてたの?」
「う、いや…」
「ふーん、貰おうとしてたんだ?へぇぇぇぇ?」
「……っうう」
声は穏やかなのに、口調は詰問のそれだ。
そして常と変わらぬ笑顔が怖い。
常から感情を表情に直結させることの少ない佐助だが、今は物凄く捻くれた表し方をしている気がする。
こちらに恐怖を与えている点に関しては成功と言えるが、そんなところで器用な真似しないで欲しかった。
しかしどれほど佐助が怖くとも、ここで折れるわけには行かない。
本当に楽しみにしていたのだ。このハロウィンを。
何もしなくても菓子を貰えるなんて、お返しを必要とするバレンタインよりも楽しい祭りではないか。
わざわざ事前に「お菓子楽しみにしてて」なんて声を掛けられたことまである。
これを待ちわびて何が悪いというのだ!
「…少しくらいなら、良いだろう」
半ば開き直ってそんなことを言えば、その瞬間佐助の笑顔が凍りついた。
最近寒くなってきた気温だが、この教室だけ何だかおかしいくらいの冷気を感じる。
寒さには強いはずなのに、ぞくりと悪寒が走るほどだ。
それと一緒に何処かで緒の切れた音も聞こえた気がした。
…気のせいならありがたいが。
しかしそんな幸村の思惑とは裏腹に、佐助が一気に爆発した。
それはもう恐ろしい勢いで。
「…っざっけんなよこの野郎!!」
「うぐっ」
「昨日あんたが晩飯前にどんっっだけ菓子食ったかちゃんと覚えてる?!お徳用のキットカットとパイの実一袋、俺が土曜の来客用に買っといた梅元の饅頭!冷凍庫の今川焼きも綺麗に三つ無くなってたし、部活帰りにマックフルーリー食った上にホットアップルパイ?!俺が帰ってきた時はキャラメルコーン食いながら出迎えたよなあんた?!一体どんな胃袋してんだよ!」
佐助の絶叫を聞いてクラスメイト達が胸元を押さえた。
聞いただけで胸焼け起こしたらしい。
「腹が減っておったのだ」
「だからって食いすぎ!そんで晩飯食えないなんて最悪じゃねぇかっ!」
「お前の帰宅が遅いのが悪い!!」
「へぇぇぇぇぇ?!そういうこと言っちゃうんだ?!」
何故か勝ち誇ったように佐助が冷笑を浮かべた。
これは不味い。
前言撤回しようと口を開いたが、佐助の方が早かった。
「今度大将呼ばれた時には“旦那の晩飯作んないといけないんでお断りします”ってちゃーんと言っとくから!」
「すっすまぬ!!俺が悪かったぁぁぁぁ!!いいいっい言うなよ!!言わなくて良いぞ!!うおおおぉおおおやおやおやお館様にお会いしていたなら何故それを言わぬのだっ?!そそそそそれなら俺もちゃんと…」
「あんたの携帯にメール入れといたけど」
「んなっ?!」
慌てて鞄の中から携帯を取り出せば、メールが届いていることを知らせるランプが点滅している。
震える手で何とか携帯を開くと、佐助の方へ向き直り、
「メールの見方が分からぬ!」
と涙目で言った。
どうも機械は苦手なのだ。
「あんたなぁっ、この間も教えただろうがっ!この真ん中のボタン押すだけ…って何で待ち受け画面に戻してんの?!あーもうっこの手紙のマークんとこ押して…そんで」
何とかメールの見方を教えてもらい、確認すれば
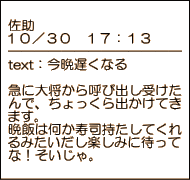
としっかり画面に映し出されていた。
「…さ、佐助」
「何?」
ぎぎぎと上手く動かぬ首を何とか廻らせて佐助に問いかければ、今から幸村が言おうとしていることを分かりきっている、とでも言うように笑っていた。
ああしまった…。
その時点で己の失態を悟ったが、先を続けねば答えは返ってこない。
ごくりと喉を鳴らすと、既に消えかかっている勇気を振り絞って口を開いた。
「昨日、俺が食べ切れなかったあの寿司は…」
「大将が俺らにって持たしてくれたやつ」
すぱっと容赦なく放たれた佐助のその言葉に、幸村はぐしゃっと崩れ落ちた。
「お…お館様のお心遣いを無駄にすることなどあってはならぬ所業…!!佐助っ!!介錯は頼んだ!!」
「あっはっはー!ふざけんなよこの馬鹿主」
鞄に仕舞った小太刀を取り出そうとしたところを蹴られて阻まれ、その乱暴な仕草を非難しようと見上げた瞬間、顔を上げたことを後悔した。
目に映った光景は外から差し込む光を背に冷笑を浮かべる佐助。
逆行が上手い具合に顔に影を落とし、これ以上無いほど恐ろしい表情になっている。
しかも声音は地を這うほど低いのだ。
「今日という今日はもう流石の俺様も頭に来たからね。こんなお馬鹿なことを笑って許容してやるわけにゃあいかないんだわ…。分かる?この言い表せないほどのやるせなさを?」
「お…うお」
「寿司に関しては生もの全般俺が片付けたよ。食いすぎて気持ち悪いわこん畜生。日持ちのするのはあんたの弁当に詰め込んであるから絶対食え。時間が経って固くなったシャリだろうがもう関係無え」
抑揚の無いその声はすらすらと低く言葉を紡いでゆく。
佐助は普段から幸村に甘いが、本気で怒らせたときの怖さと言ったらもう、紅蓮の鬼ですら裸足で逃げ出したくなるような恐ろしさなのだ。
そして今現在幸村は裸足で逃げ出したい。
「俺を本気で怒らせるとどういう目に合うか、思い知らせてあげるよ」
にやり、と今まで見たことの無いような笑みをこちらへ向けて、佐助は自分の席へ悠然と腰掛けた。
冷えた空気は消えることはなく、固唾を呑んで様子を見守っていたクラスメイト達も動けない。
そして渦中の人物である幸村が動けないことは言うまでも無かった。
ごめんなさい。
後から考えれば、ここで素直に謝っておけばよかったのだ。
許してもらえるまで何度も。
「ううううううううぅぅぅぅぅ…」
革張りの上質なソファの上に膝を抱えて蹲り、リビングテーブルの上に並べた今日の戦利品を眺めつつ唸った。
どこを見てもブラックガムブラックガムブラックガムブラックガムブラックガムブラッグラム…あれ何かおかしい?
「どこまでお前は根回しが良いのだ…」
現在洗い物中の佐助の背に向かってそう呟けば「俺様を誰だと思ってんの」という自信満々の答えが返ってきた。
これに何も言い返せないのが悔しい。
貰えたお菓子が全部ブラックガムだという事からも分かるように、今日は完全に幸村の負けだった。
わざわざ手作りのお菓子を渡そうと用意してくれていた者にまで根回しし、「今度からそんなにお菓子食べ過ぎたら駄目だよ」という説教と共にブラックガムを渡される始末。
本気で凹んだ。
こうなったら買い食いでもして気を紛らわせようと思い売店へ足を運べば、菓子パン系が全て売り切れているという悪夢。
どうして今日に限ってっ…!!と打ちひしがれていると、佐助が冷笑を浮かべながら「糖類全面禁止だよ」と言い置いて立ち去って行った。
ここまでやるのかっ!と愕然としたが、あの笑みを前にして抗議する勇気は無い。
打つ手が無かった。
そのまま糖分を一切手に入れられぬまま授業を終えれば、放課後の部活でも山のようにブラックガムを貰った。
…泣きたくなった。
かろうじて菓子と言えなくもないブラックガムだが、この強烈なミントは流石の幸村も苦手としていた。
眠気覚ましに一つくらいなら偶に食べることもあるが、こんな山盛り貰っても一生かかって消費しなければいけないかもしれない。
毎日一枚ずつ食べたとしても、どれだけかかるか。
それを考えると目の前が暗くなってくる。
そんな感じで帰宅途中も買い食いする気が失せ、ぐったりと帰宅すればおかえりの声。
今日一日を悪夢に塗り替えてくれた張本人からの言葉だったが、怒る気力はない。
むしろ新たなる恐怖が待ち受けていないか血の気が引いてゆく。
朝の感じから言って佐助の機嫌は最悪。
下手すればカップ麺という可能性もあったため、恐る恐る食卓を除けば驚いたことにちゃんとした夕食が揃っていた。
具沢山のコンソメスープにクリームグラタン。そしてかぼちゃのサラダ。
嬉しいことにパンプキンパイまで用意してあった。
噛みしめるように食べたそれは、甘さ控えめながらも十分甘く、今日一日糖類を断たれていた身としては染みいるように美味かった。
そして何より、それを幸せそうに食べている最中、時折佐助が苦笑を洩らすようになっていたことが何より嬉しかった。
朝から今まで一貫してあの冷笑しか見せていなかったため、その恐怖はもう己の魂の根底に刻まれる勢いだったのだ。もう決して同じ轍は踏むまい。
己にそう誓った瞬間だった。
そして今、佐助は洗い物中である。
もともとはハロウィンらしい食事を用意しようとしていたらしく、飾り付け等は無かったものの今日の食事にはかぼちゃがふんだんに使われていた。
何かと器用な佐助のことだから、昨日のお菓子の一件さえなければもっと凝ったものを作っていたのだろう。
ある程度手を抜いたとはいえ食器はいつもより多く、その上パンプキンパイも焼いてくれたために鉄板やらボウルやらが乾燥機の中に散乱している。
あれだけ怒っていたというのに非情になり切れないところが佐助らしい。
そのまま佐助の背を眺めながら、手際よく食器を洗ってゆくその仕草を何となく目で追っていると、不意に思いついた。
言おうか言うまいか迷ったが、今日はハロウィンなのだ。
祭りなら、こんな箍の外れた言葉も許されるのだろう。
そう己に言い聞かせて口を開いた。
「佐助、トリックオアトリート」
流石にこの状況でお菓子をもらえるとは思っていない。
それどころかまた佐助が怒りだしそうな台詞だ。
案の定佐助は呆れた声で
「んなもん上げるわけ無いでしょうが」
とため息交じりに答えた。
洗い物の手を止めようともしないその返答は、明らかに適当に相槌を打っただけという風体だった。
しかしそれにへこたれずにソファから立ち上がると、こちらに背を向けたまま作業を続ける佐助へ近づいて更に続けた。
「やはり、くれぬのか」
「あったり前でしょ。この期に及んでそんなこと言うとは…あんたまだ懲りて無いわけ?」
だんだん下降してきた機嫌を肌で感じつつ、すぐ傍で立ち止まれば佐助がこちらへ視線を寄こした。
目には不機嫌な光が宿っている。
普通はここで反省したような表情を作るのだろうが、今日に限ってはにやりと笑って返してやった。
今日はハロウィンなのである。
お菓子かいたずらかと問うたのに、この男は“菓子をやらない”と答えたのだ。
それならやるべきことは一つだ。
その目をじっと見つめたまま、スポンジを掴んだままの泡だらけの手をとるとぐいと力を込めて引き寄せた。
「何?お菓子はあげないって…、っ」
言葉を遮るようにその唇を奪えば、面白いほどその体が固まった。
動かなくなったことを良いことに、噛みつくようにその唇へもう一度口付けて、そのままにやりと笑ってから離れる。
目の前で目をかっ開いたまま動かない佐助は、まるで時を止めたかのように瞬き一つしない。
その様子がどうにもおかしく、更に笑みを深めると、そっと耳元に唇を寄せた。
「菓子をくれぬのが悪いのだ」
そう一言言い置いて踵を返せば、佐助の手からスポンジが落下する音が聞こえた。
キッチンから出る瞬間にその姿を覗き見れば、余程のことがない限り変わらないはずの顔色を朱に染めて未だに固まっている姿が見えた。
それに釣られて己の頬に熱が昇るのも感じつつ、後ろででドアを閉めると直ぐ様自室へと走る。
自分から仕掛けたとは言え、こういったことには未だに耐性が付いていない。
徐々に早鐘を打ち始めた鼓動を必死で抑えつつ、明日の朝どういう顔をして佐助に会えばいいか本気で悩んだ。
多分、明日まで答えは出ない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
甘っ。
私が書く文章の中ではかなり甘めかと…。
現代設定の真田主従の一つめ。
うおおう…。
実はこれ、甘さ控えめに書いた方でして、別verもあるのです。
幸村の「トリックオアトリート」の続きから始まります。
「胸やけなんて気にしない☆」という心の広いお方は下で砂糖を足してお進みください。
砂糖を加えてみる。
ブラック・ブラック・ブラック